
2025年12月18日(木)、シャングリ・ラ東京で開催された「ISV Growth Forum ─ AIネイティブ時代を勝ち抜くための...

ロードマップとは、プロジェクトの方向性やスケジュール、タスクを整理した計画表・工程管理表のことです。ロードマップを作成することで、プロジェクトの目的・スケジュール・行動が明確になり、認識の統一とスムーズな情報共有が可能です。
本記事では、ロードマップの概要や作成する目的とメリット、作成ステップ・ポイントについて詳しく解説します。ロードマップについて知りたい方、利用したい方は、ぜひ参考にしてください。

ロードマップ(Roadmap)とは、ビジネスにおいてプロジェクトや事業の方向性・計画を時系列で表したもののことです。直訳すると「道路地図」や「工程表」「進行計画表」という意味を持ちます。
ここからは以下の事項について解説します。
ロードマップは大きく以下の2種類に分かれます。
順に解説します。
プロジェクトに関する方向性やスケジュール、タスクを整理したものです。一目で全体像を把握でき、共通認識を持って推進可能です。一般的にロードマップといった場合、多くの人がプロジェクトロードマップをイメージします。
製品の開発や改善、展開に向けた施策などをまとめたものです。以下の戦略や計画が盛り込まれており、遅延なく製品をリリースする際に役立ちます。
製品の開発からリリースまでのロードマップを作成する際には、開発部門だけでなく営業やマーケティング部門も含めて作成・共有するケースが一般的です。
ロードマップとマイルストーンは混同されがちですが、両者は役割が異なります。ロードマップはプロジェクトなどの全体像を表し認識の統一やタスク管理に利用されるのに対して、マイルストーンは進捗に遅れが出ていないかなどを確認するための通過地点として設定されます。ロードマップには詳細なタスクなどを記載しないため、プロジェクト期間が長期に及ぶ場合計画のズレが把握しにくくなるケースが少なくありません。ロードマップ内に中間目標としてのマイルストーンを設定して、進捗管理を行います。
ロードマップとスケジュール表の違いは、対象期間と粒度です。ロードマップは長期間の計画を表す際に活用されるケースが一般的で、詳細なタスクなどは記載しません。一方、スケジュール表には短期的かつ具体的なタスクが記載されます。ロードマップは長期的な戦略の推進や管理に適しており、スケジュール表は日々のタスク管理に最適です。
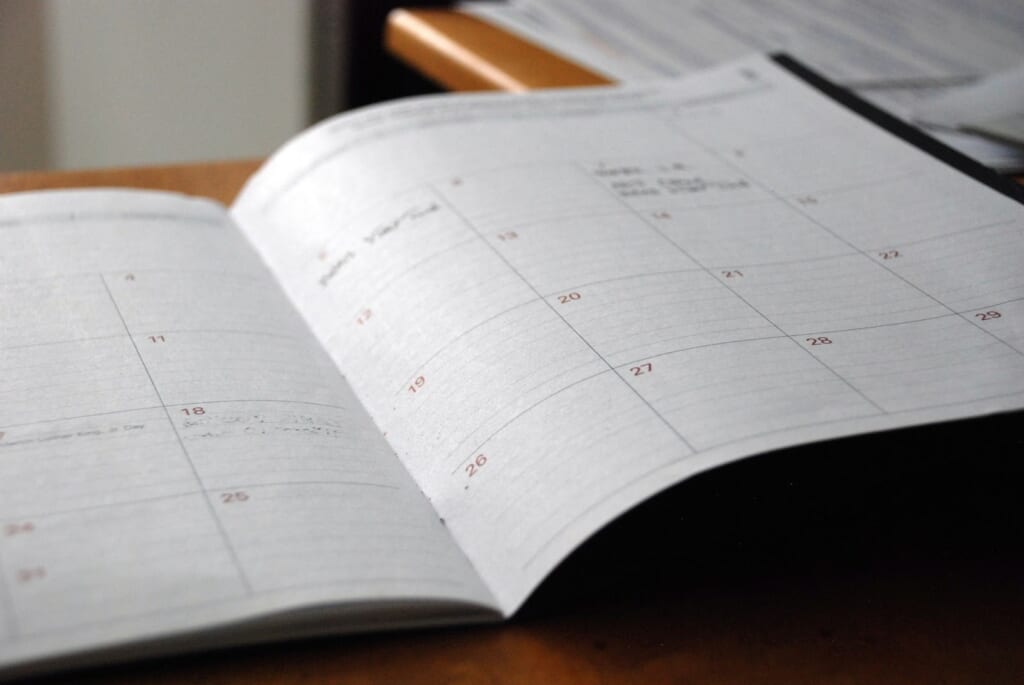
ロードマップを作成する目的とメリットは以下の3つです。
ここからは、上記それぞれのメリットについて解説します。
ロードマップを作成する最も重要な目的は、最終目的とそこに至る道筋の明確化です。なにをいつまでに達成するかを明確にすることで、実施しなければならないタスクとその期限が明らかになります。メンバーのモチベーションが向上するとともに、効率的な推進が期待できます。
スケジュールや行動の明確化も、ロードマップを作成するメリットです。目標があっても行動しなければ達成できません。また、従業員は基本的に日々の業務で忙しいため、期限を設けない場合いつまでたっても行動しないでしょう。ロードマップは、タスクの設定や進捗管理に役立ちます。
認識の統一と適切な情報共有の実現も、ロードマップを作成するメリットです。プロジェクトは複数のメンバーで推進することが多く、認識がズレるとタスク処理の遅延や重複などが発生します。ロードマップを基に会話をすれば、メンバーの認識を統一しやすくコミュニケーションミスも防止できるでしょう。
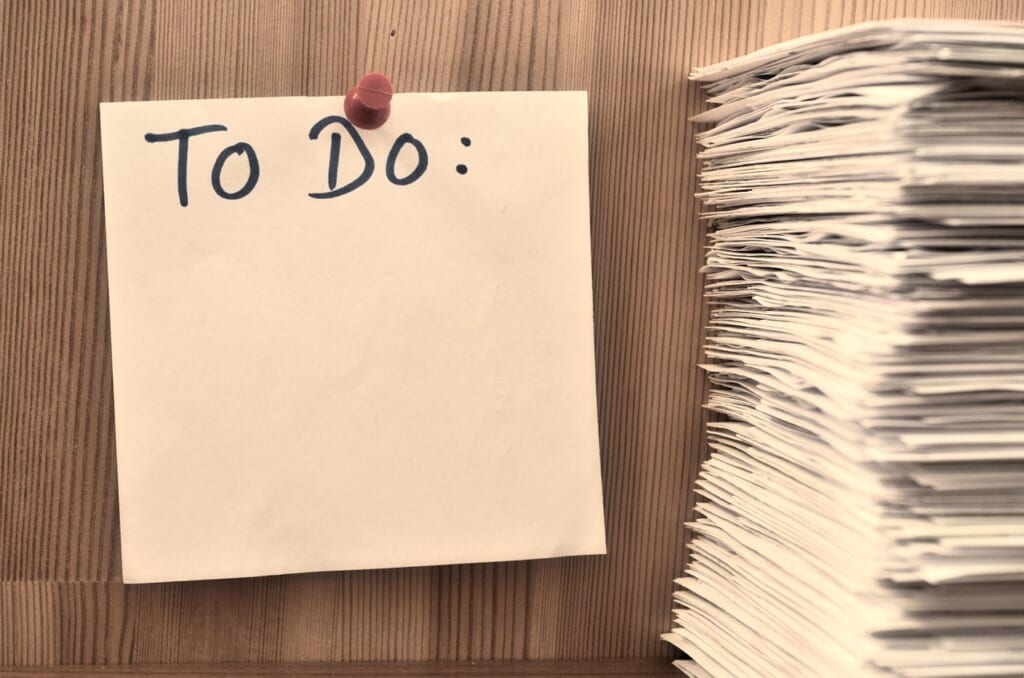
ロードマップを作成する際のステップは以下の通りです。
ここからは、上記それぞれのステップを順に解説します。
まずは、関係者全員が理解できる具体的で達成可能な目標・ゴールと期限を定めます。例えば「〇月〇日までに〇〇円の売上を上げる」「〇月〇日に新製品〇〇をリリースする」といったイメージで定量的な設定が重要です。期限を短くし過ぎると無謀な計画になってしまうため、多少余裕を持った設定が良いでしょう。達成できないロードマップでは意味がありません。
続いて、現状を分析して目標との差や状況を明確にします。例えば、売上目標の達成を定めた場合、現状の売上はもちろんメンバー・ツールなどのリソースや顧客数も棚卸しします。
現状を把握後、目標と比較して問題点を洗い出しましょう。問題点を整理すれば、目標達成に向けどのようなタスクを行う必要があるかを把握できます。また、プロジェクトを推進する過程で発生する可能性があるトラブルを洗い出すことも重要です。事前にトラブル・リスクを想定しておけば、問題が起こっても冷静に対処できるでしょう。問題点・リスクなどを一通り棚卸ししたら、解決策も検討します。
目標や現状の分析、課題の洗い出しと解決策の検討が終わったら、スケジュール・実施事項などを可視化します。作成時には、図やチャートなども活用して誰でもわかりやすいように工夫することが重要です。また、プロジェクトが長期間に及ぶ場合にはマイルストーンを設定して、中間で進捗確認できるようにしましょう。なお、作成時に利用可能なフォーマットは後ほど詳しく解説します。
最後に、完成したロードマップをプロジェクトメンバーなどの関係者に共有します。内容を共有することで、各個人の役割や責任範囲が明確になりモチベーションアップが期待できます。関係者から変更・修正に関する意見が出た場合には、再度話し合い必要に応じて修正・変更を行うと良いでしょう。
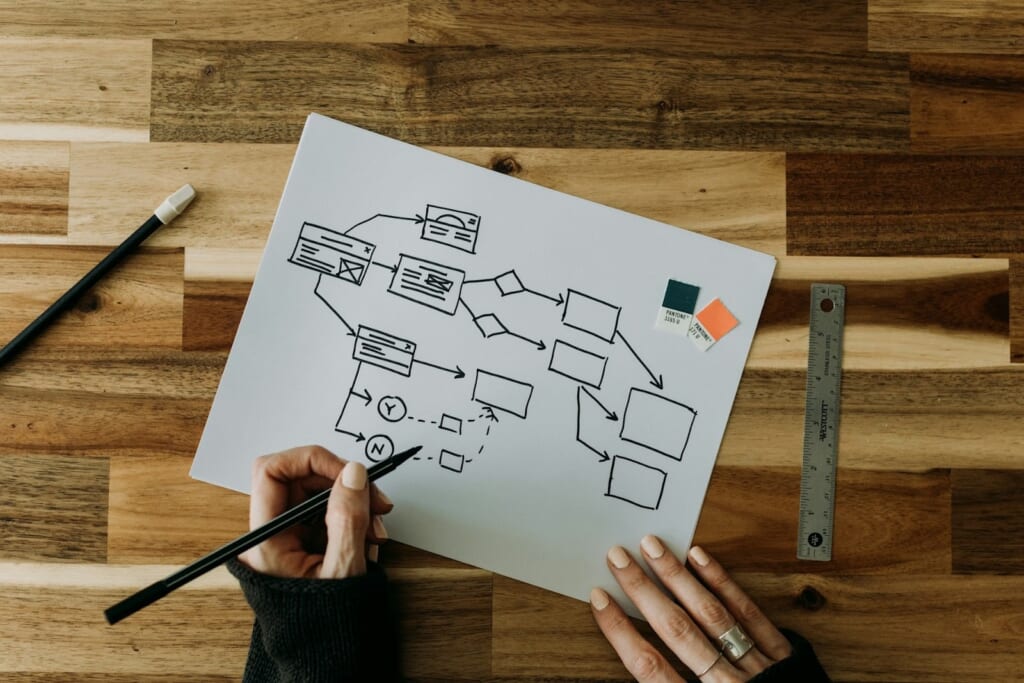
ロードマップの作成に役立つ主なフォーマットは以下の通りです。
順に解説します。
プロジェクトの目標やタイムスケジュールをまとめた表です。タスク間のつながりや優先順位が時系列で可視化され、効率的に作業を進められます。また、他のフォーマットと比べて比較的容易に作成可能です。
記号・図を用いて、プロセスやフローをわかりやすく可視化したものです。視覚的に理解しやすい点が特徴で、メンバーとの認識統一を図れるでしょう。ただし、複数の記号や図を用いると見にくくなるため注意が必要です。
目標達成に向けて必要なタスクを洗い出し、リスト化したものです。他のフォーマットと比べて、タスクを詳細に洗い出すため抜け漏れの発生を防止できます。ただ、あまりに細かなタスクを記載すると全体像の把握が困難になる恐れがあります。WBSをロードマップとして活用する際には、タスクの粒度と見やすさのバランスを検討しましょう。
開始時から完了日までに実施するタスクやスケジュールを帯グラフで表したもので、ロードマップで最も用いられるフォーマットです。目標や期限を記入でき進捗管理がしやすい点が特徴で、Excelやスプレッドシートでも作成できます。

最後に、ロードマップ作成時における以下のポイントについて解説します。
ロードマップの作成時には、目標達成期限を明確に定めましょう。期限が不明確な場合、なにをいつまでに行う必要があるかが明らかになりません。中間目標として設定するマイルストーンの期限も明確にすることが重要です。
適切なマイルストーンの設定も欠かせません。適切なマイルストーンの設定は、メンバーのモチベーション維持に有効です。ただ、細かく設定しすぎると重要なポイントがぼやけてしまいます。マイルストーンは、一週間・一ヵ月などの区切りや年末・イベント時といった節目に設定すると良いでしょう。
目標や成果指標は定量的に設定しましょう。数値に落とし込まれていない定性的な目標の場合、客観的な評価が困難です。プロジェクトが問題なく進んでいるか、遅延しているかの判断もできないでしょう。数値を用いた目標の設定が重要です。
クリティカルパス法とは、プロジェクトを完了させるために行う必要がある重要なタスクを特定する手法のことです。クリティカルパスがプロジェクト全体のスケジュールに最も影響を与えるため、クリティカルパス上のタスク実施・完了が遅れると全体の計画も遅延します。クリティカルパス法を用いることで、重要なタスクの見極めが可能となり現実的なスケジュールを設定できます。
わかりやすさ・見やすさへの配慮も作成時のポイントです。ロードマップにおける一つの役割は、プロジェクトの流れを大まかに把握することです。情報を記載し過ぎると、内容が複雑になり目標や方向性が把握しにくくなる恐れがあります。わかりやすさ・見やすさも踏まえた上で、記載する情報や期間の単位を設定すると良いでしょう。
ロードマップをわかりやすく見やすくするために、タスクを細かくし過ぎないことが重要です。重要なタスクやメインタスクのみを記載して、全体像を把握できるようにします。詳細なタスクは別のツールで管理すると良いでしょう。

ロードマップとは、ビジネスにおいてプロジェクトや事業の方向性・計画を時系列で表したもののことです。大きくプロジェクトロードマップとプロダクトロードマップの2種類に分けられ、作成することで目的・スケジュール・行動が明確になります。作成時には、まず目標と達成期限を決め現状の把握と問題点・タスクの洗い出しを行いましょう。また、わかりやすさや見やすさを意識することも欠かせません。詳細なタスクを記入し過ぎると、重要な情報を把握しにくくなります。
ロードマップを活用して、効率的にプロジェクトを推進しましょう。