
10月22日(水)~24日(金)に幕張メッセにて、Japan DX Week2025秋が開催されました🍂 今回も弊社SMSデータテック...

近年、企業のITインフラは複雑化の一途をたどっており、その運用・管理を効率化する手法として注目されているのが「ITOM(IT Operations Management)」です。ITOMはシステムの稼働状況を可視化し、トラブルの早期検知や業務自動化を実現して、IT部門の負担軽減とビジネス全体の安定稼働に貢献できる手法です。本記事では、ITOMの概要から導入メリット、そして実施にあたっての課題や成功するためのポイントについて解説します。

ITOMとは、企業のITインフラやサービスの運用を効率的かつ安定的に管理するための総合的な取り組みです。具体的には、ネットワークやサーバー、アプリケーション、クラウド環境などの構成要素を一元的に監視・分析し、障害の予兆検知や自動修復、リソースの最適配分などを通じて、業務継続性とパフォーマンスの最大化を図ります。
ITOMは単なるシステム監視にとどまらず、AIOpsや自動化ツールと連携させることで、IT部門の負担を軽減しながら、より高度な運用体制を構築できるのが特長です。
ここでは、ITOMが求められる背景とITOMと混同されやすい「ITSM」や「ITAM」との違いについて解説します。
ITOMが求められる背景には、まずITインフラの複雑化があります。クラウドサービスや仮想化、マイクロサービスの普及により、従来のような単一構成ではなく、オンプレミスとクラウドが混在するハイブリッド環境が主流となり、統合的な運用管理が求められるようになっています。
また、システム障害の影響がビジネスに与えるダメージも増大しており、単なる復旧対応ではなく、予兆検知や自動復旧などのプロアクティブな運用への移行が急務です。さらに、近年ではITが単なる業務基盤ではなく、ビジネス価値そのものを生み出す存在として位置づけられており、IT運用にも戦略的な視点が求められています。
現在のITおよびビジネスを取り巻く環境の変化に適応するために、ITOMが注目されるようになっています。
ITSM(IT Service Management)は、ITサービスを企画・設計・導入・運用・改善というライフサイクル全体を通じて管理し、ユーザーへの価値提供やサービス品質を重視する枠組みです。一方、ITOMは、ITSMの「運用(Operations)」部分に焦点を当て、インフラやネットワーク、サーバー、アプリケーションなどの基盤要素を監視・制御・最適化することを主な役割とします。ただし、両者は排他的ではなく、相互補完の関係にあり、ITOMで検知した異常をITSMに自動で連携できます。
なお、ITSMの詳細は以下をご覧ください。
⇒ITSMとは?おすすめツール5選や導入メリットと成功のポイントを解説
ITAM(IT Asset Management)は、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなどのIT資産を取得から廃棄までのライフサイクル全体で管理・最適化する枠組みです。一方、ITOMは、これらの資産が実際に運用される環境を安定的かつ効率的に動かすことに焦点を当てます。ITAMとITOMは統合・連携させることで大きな価値を発揮し、例えば、ITOMで発生したアラートや障害に対し、ITAMの資産情報が紐づいていれば、故障対応や交換判断が迅速になります。また、ITAMがもつライセンスや使用状況のデータを、ITOMが監視する実際の稼働データと組み合わせて、無駄なライセンス費用の削減や適正化につなげることも可能です。
なお、ITAMの詳細は以下をご覧ください。
⇒IT Asset Managementとは?目的やメリットやおすすめツールを解説
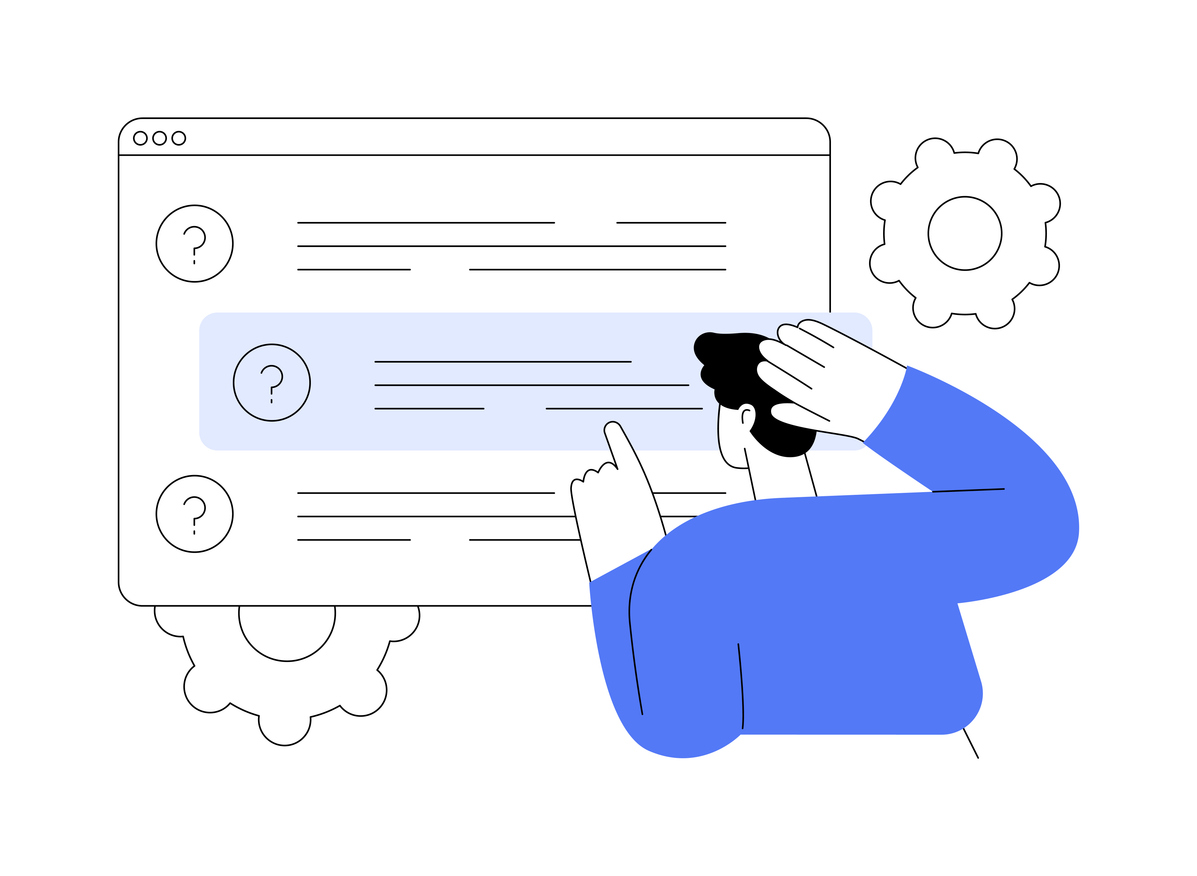
ITOMの主要な役割は主に以下の3つです。
ここでは、上記の役割について解説します。
ITOMにおけるネットワークインフラストラクチャの管理は、企業の通信基盤を安定的に維持し、全システムの可用性を確保するための中核的な役割を担います。ルーターやスイッチ、ファイアウォール、ロードバランサーといったネットワーク機器の構成管理・稼働監視を行い、障害や性能低下を未然に防ぐのが主な内容です。
ITOMの役割の一つとして挙げられる「ヘルプデスク」は、エンドユーザーとIT運用の接点を担う存在であり、社内・顧客からの問い合わせや障害報告を受け付け、適切に処理・対応する業務を含みます。具体的な業務内容の例は以下の通りです。
ITOMにおけるヘルプデスクは、ユーザー対応を受け身でこなすだけでなく、運用監視と密接にリンクし、自動化や効率化を推進する役割を果たす重要な構成要素です。
ITOMにおける「エンドポイントの管理」は、企業内外のあらゆる端末を統合的に制御・監視し、安全性と可用性を維持する重要な役割です。エンドポイントは利用者との接点でありながら、サイバー攻撃や操作ミスなどによるリスクの発生源にもなり得るため、常時かつ包括的な管理が求められます。
エンドポイントの管理では、各端末に対するパッチ適用やアップデートの自動配信、セキュリティ設定の統制、ウイルス対策ソフトやEDR(Endpoint Detection and Response)の導入といった施策が行われるのが一般的です。ITOMにおけるエンドポイントの管理は、単なる資産管理ではなく、業務継続性とセキュリティの両立を支える中核的な運用要素として位置づけられています。

ITOMを導入するメリットは主に以下の3つです。
ここでは、上記のメリットについて解説します。
ITOMを導入すれば、システムトラブルの予測が可能になります。各種ログや監視データをリアルタイムに分析し、CPU使用率の急上昇やメモリ異常などの障害の兆候を事前に検知して、対応を前倒しにできます。また、AIOpsなどの技術と組み合わせれば、自動でアラートを発し、重大な影響を及ぼす前に復旧措置を取ることも可能です。
ITOMの導入により、システム障害などの被害を最小限に抑えられます。異常を早期に検知し、自動で対応を開始する仕組みにより、トラブルの拡大や長時間のダウンタイムを防止し業務への影響や売上損失、顧客離れなどのリスクを大幅に軽減可能です。また、復旧対応の迅速化により、人的リソースやコストの負担も抑えられます。
ITOMは、運用コストの削減にも役立ちます。例えば、定型業務の自動化により人件費を抑えられ、サーバーやストレージなどのリソースの最適化が実現可能です。また、障害対応の迅速化により復旧費用や業務停止による損失も低減できます。

ITOMの実施における課題は主に以下の3つです。
ここでは、上記の課題について解説します。
ITOMの導入の際には、初期費用や運用面での手間が大きな課題となる場合があります。まず、導入初期には監視対象の設定やツールの整備、構成管理(CMDB)の構築など多くの作業が必要です。また、監視ツールや自動化システムなど複数のツールを導入することで、ライセンス費用や保守費用も増加し、運用後もアラートの調整やツールの更新、他システムとの連携作業など、継続的な工数がかかります。
ITOMを導入しても、システム全体の可視化がうまく進まないケースがあります。例えば、クラウドとオンプレミスが混在していたり、監視ツールと資産管理ツールがバラバラに使われていたりすると、情報が分断されて全体像が見えなくなります。また、マイクロサービスやコンテナ環境では構成が常に変化するため、静的な可視化では追いつきません。さらに、ノイズの多いアラートやセキュリティ上のアクセス制限も、可視化の精度を下げる要因になります。
ITOMを導入しても、システムの拡張が思うように進まないケースがあります。主な原因は、既存ツールや基盤が小規模向けに設計されていて、急なリソース増加やクラウド拡張に対応できない点にあります。
また、他システムとの連携が複雑すぎると、新しい機能の追加や構成変更のたびに調整が必要となり、拡張性を大きく制限される点には注意が必要です。さらに、監視対象が増えることでデータ量やアラートが急増し、処理が追いつかなくなる場合もあります。

ITOMを効果的に実施するポイントは以下の3点です。
ここでは、上記のポイントについて解説します。
ITOMによるシステム運用の効率化や自動化は、IT部門だけの課題ではなく、全社的なコスト削減やリスク管理、事業継続性に直結する項目です。ただ、ITOMの導入にはさまざまなコストがかかるため、経営層の理解を得る必要があります。
経営層の理解を得るためには、まずITOMの効果を「ビジネスへの貢献」として伝えるのが効果的です。例えば、「障害による売上損失を防げる」「人件費を削減できる」など、経営に響く指標で説明すると理解を得られやすくなります。また、段階的な導入計画や他社の成功事例を示すと、導入の現実性と価値も伝えられます。
ITOMを効果的に実施するには、「何を達成したいか(目的)」を明確にし、それを踏まえて「優先順位」を定める必要があります。まず、例えば障害ダウンタイムの削減、運用コストの最適化、サービス可用性の向上などのビジネス価値につながる目的を定義し、その後優先順位をつけてフェーズ分けすると導入後の運用がスムーズに進められます。
ITOMを効果的に進めるには、専用ツールの活用が不可欠です。専用ツールでは、まずインフラやサービスの構成を自動で発見・可視化できる「Discovery機能」や、アラートの整理・優先付けができる「イベント管理ツール」を導入するのが基本です。また、パッチ適用や再起動などの作業を自動化できる「オーケストレーション機能」や、ITSM・ITAMと連携可能なツールを選ぶと、業務の効率化が進められます。適切なツールを導入すれば、トラブルの早期発見や対応の迅速化、人的コストの削減が期待できます。

ITOMツールは、複雑化・分散化するIT環境を一元的に管理し、トラブルの早期発見や運用の自動化、リソースの最適化を支援できる点で有用で、ITOMを運用するのには欠かせないものといえます。
ここでは、ITOMツールに備わる主要な機能と、それらを活用することで得られるメリットについて解説します。
ITOMツールの代表的な機能は以下の通りです。
ここでは、上記の機能について解説します。
ITOMツールにおける構成管理機能は、サーバやネットワーク機器、ソフトウェアなどのIT資源を自動で検出・記録し、関係性や変更履歴を一元管理する機能です。構成管理データベース(CMDB)を活用して、システム全体の構成を可視化し、障害時の影響範囲や変更の影響をすばやく把握できます。また、設定ミスや構成のズレも早期に検知でき、安定した運用につながります。
ITOMの土台として、他の監視機能や自動化との連携にも欠かせない重要な機能です。
ITOMツールの監視・可観測性機能は、システムの異常を早期に発見し、原因特定と迅速な対応を可能にする重要な機能です。監視では、CPU使用率やメモリ使用量などのメトリクスやログを収集し、設定したしきい値を超えた場合にアラートを出します。一方、可観測性では、ログ・メトリクス・トレースを組み合わせて相関分析を行い、複雑な障害の原因や発生パターンを把握します。監視・可観測性機能により、単なる異常検知だけでなく、「なぜ・どこで」問題が起きたのかを特定しやすくなるため、運用の質とスピードが大幅に向上可能です。
ITOMツールのイベント管理機能は、システムから発生する大量のイベントやアラートを整理・分析し、本当に重要な異常だけを抽出して対応につなげるための機能です。イベント管理機能では、イベントの収集と正規化、関連イベントのグルーピング(相関分析)、アラートのノイズ削減を行い、必要に応じて自動でインシデントを起票します。また、CMDBと連携すれば、影響範囲を特定しやすくし、自動対応のトリガーとしても活用できます。
ITOMツールを適切に導入・運用すれば、以下のようなメリットを得られます。
上記のメリットが得られるITOMツールとして多くの企業で導入されているのが「ServiceNow ITOM」です。ServiceNow ITOMの特徴については次項にて解説します。
ServiceNow ITOMは、IT運用の自動化・可視化・効率化を支援するプラットフォームで、以下のような特徴を持っています。
上記の特徴により、ServiceNow ITOMは運用効率化、トラブル早期対応、運用コスト削減といった効果を実現できる点で多くの企業に支持されています。

ITOMは、ITインフラの可視化・自動化・最適化を通じて、運用の効率化と安定性向上を実現する重要な取り組みです。ITOMの特徴を踏まえた構成管理や監視、イベント管理などの機能を備えているITOMツールを活用すれば、障害の予兆検知、迅速な対応、運用コストの削減などの多くのメリットが得られます。ITOMツールのなかでも、ServiceNow ITOM はさまざまな機能を網羅した高度なITOMプラットフォームですが、導入・運用の際には専門的な設計や開発、継続的なチューニングが欠かせません。そこでおすすめなのが弊社SMSデータテックの「ServiceNowの導入・開発・保守運用」サービスです。ServiceNowの導入・開発・保守運用なら、企業ごとのIT課題に応じたカスタマイズや、スモールスタートからの段階的導入にも対応しており、安心して導入・運用を進められます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。