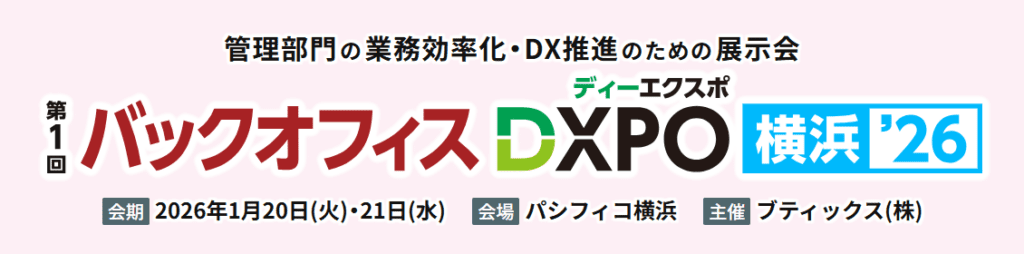
弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...
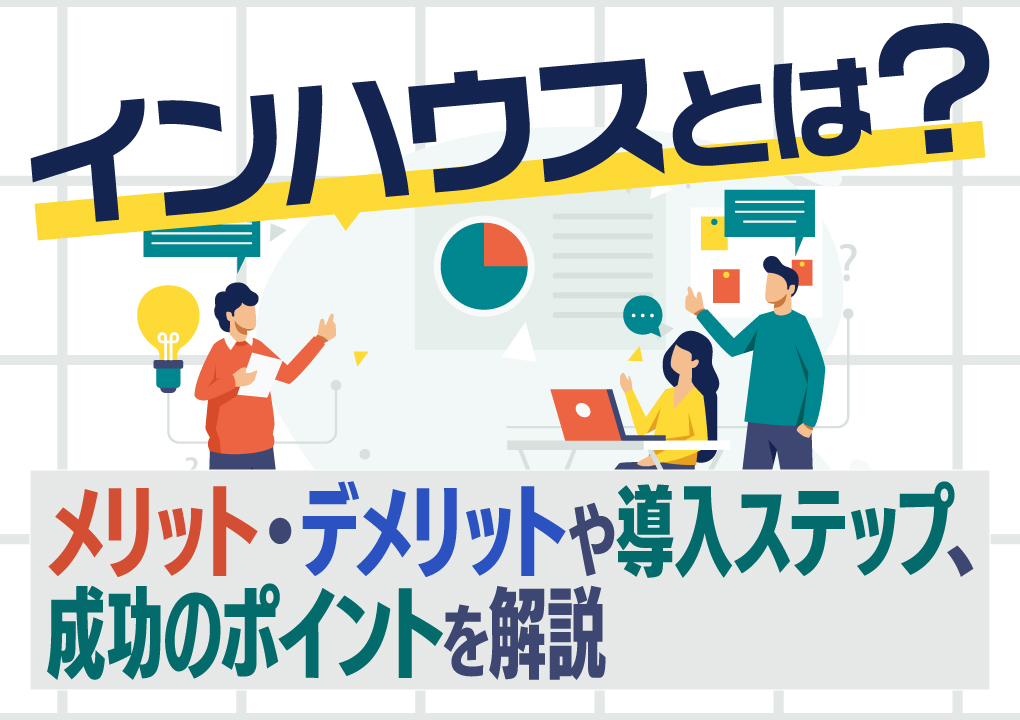
インハウスとは、企業内部で業務を処理することです。例えば、外注していたWebコンテンツの記事を社内で作成することが該当します。インハウスには、メリット・デメリットの双方が存在するため、企業の状況に応じて導入するかの判断が重要です。
本記事では、インハウスの概要やメリット・デメリット、導入ステップと成功のポイントについて詳しく解説します。インハウスについて知りたい方、導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
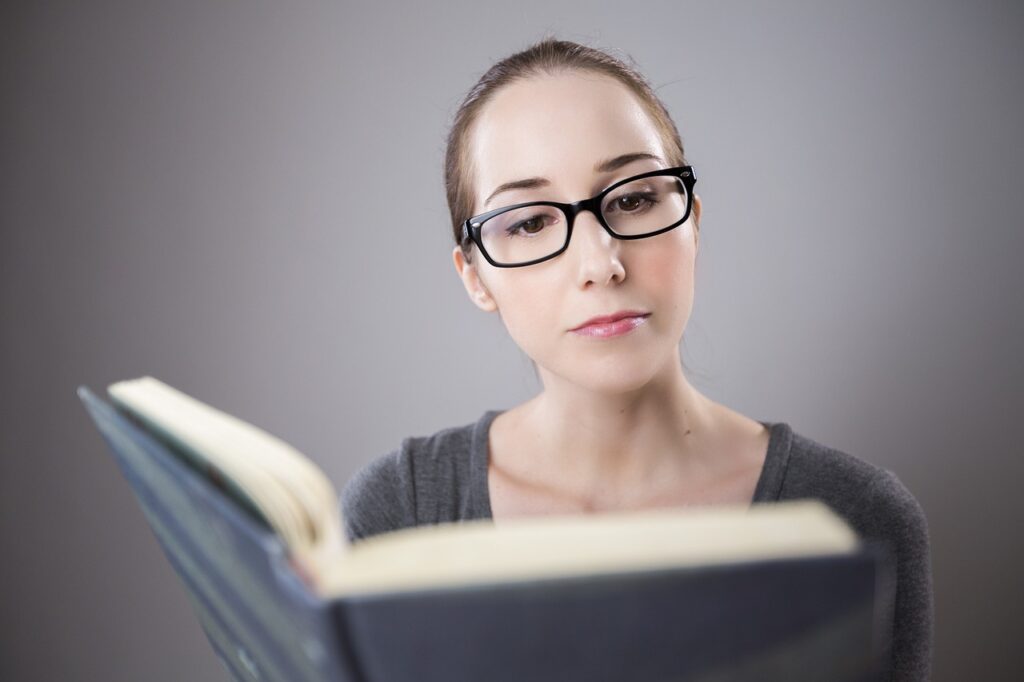
インハウス(in-house)とは、企業がアウトソーシング(外部委託)せずに企業内で業務を行う(内製化)ことです。また、グループ内企業で業務を処理することもインハウスです。例えば、外部企業に委託していたコールセンター業務を社内で実施することが該当します。
対義語として活用されるインハウスとアウトソーシングの主な違い・比較は、以下の通りです。
| インハウス | アウトソーシング | |
|---|---|---|
| 導入ハードル | 高い | 低い |
| 業務に対する柔軟性 | 高い | 低い |
| 社内へのノウハウ蓄積 | しやすい | しにくい |
| 新たな情報の獲得 | しにくい | しやすい |
| 主な発生コスト | 採用・教育費、人件費 | 外注費 |
| コストコントロールのしやすさ | しにくい | しやすい |
インハウスとアウトソーシングは、それぞれ異なる特徴を有しています。
アウトソーシングの場合、必要なときに必要な人材に力を借りることが可能です。単価は上がりますが、専門人材の確保もしやすいでしょう。ただ、社内へノウハウが溜まりにくい点がデメリットです。
一方、インハウスであれば社内にノウハウを蓄積できます。ただし、必要な人材を自社で採用もしくは教育しなければなりません。また、業務処理方法の検討や必要な機器の準備も自社で行う必要があります。導入ハードルが高く、安定稼働するまでに一定時間を要するでしょう。
インハウスとアウトソーシングは、どちらかが優れているというものではありません。企業の目的や状況に合わせた使い分けが重要です。
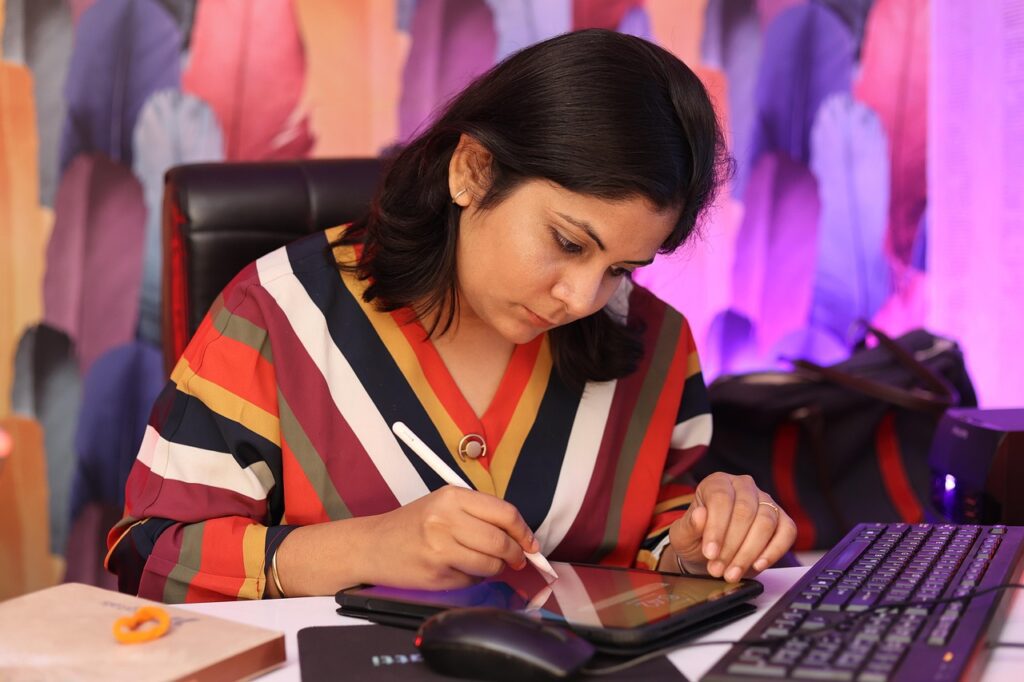
続いて、インハウスにおける代表的な以下の職種を紹介します。
インハウスデザイナーとは、デザイン会社やフリーランスに依頼するのではなく、企業内部でデザインに関する業務を行うことです。具体的には、以下デザインの検討・作成を実施します。
インハウスエンジニアは、大きく以下の2種類に分けられます。
後者は「インハウスITエンジニア」と呼ばれるケースもあり、自社で活用するシステム・アプリの設計や開発、保守・運用を担当します。
インハウスマーケターとは、自社でマーケティング業務を行うことです。例えば、以下を外部に委託せず自社内で実施します。
専門性の高いマーケティング業務をインハウスするのは簡単ではありません。ただ、専属のマーケターが居れば大きな強みになるでしょう。
インハウスSEOとは、自社サイトで成果を挙げるための施策検討・実行を社内で行うことです。具体的には以下の業務を行います。
スマートフォンの普及や購買行動の変化により、SEO対策の重要性は向上しています。ただ、SEOは短期的に成果が出にくく長期的な施策であるため、外注すると多くのコストがかかります。インハウスで社内にノウハウを蓄積できれば、コストを抑えて効果を最大化可能です。
インハウス広告運用とは、リスティング広告やSNS広告を自社で運用することです。近年は、Web広告に関する本が数多く出版されており、オンラインセミナーなども多数開催されています。また、Web広告はPDCAを回しやすいため、ノウハウを獲得しやすいでしょう。
インハウスローヤーとは、外部の弁護士事務所に業務を依頼するのではなく、社内で法律に関する業務を行うことです。例えば以下の業務を実施します。
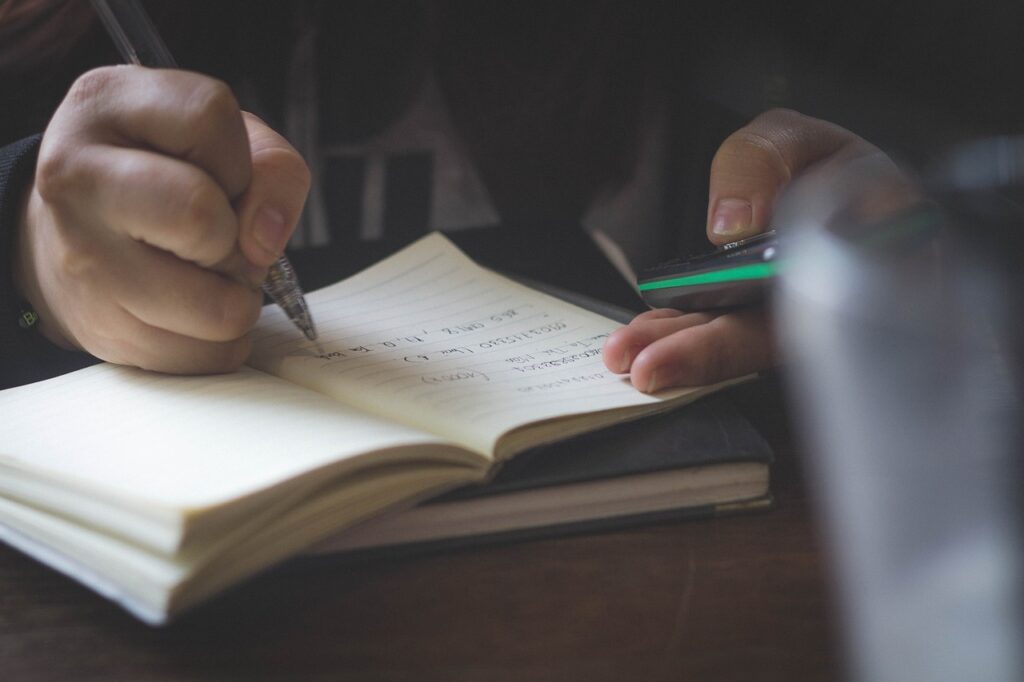
次に、インハウスにおける以下のメリットについて解説します。
インハウスであれば、成功や失敗を通して獲得したノウハウを社内に蓄積可能です。インハウスを行う場合、社内で一から設計や構築、運用を行うため、多くの経験を積めるでしょう。アウトソーシングを活用していると、基本的に業者が業務を行い社内にノウハウが溜まりません。継続的にアウトソーシングを利用しなければならない可能性があります。
人材や業務の管理がしやすい点も、インハウスのメリットです。アウトソーシングの場合、人材や業務の管理は基本的に委託業者が行います。自社での管理はできません。
インハウスの実施により、柔軟性を高められます。例えば、業務内容や処理方法を変更したいと思っても、アウトソーシングを利用している場合は委託先に相談しなければなりません。迅速に対応できず、委託先に断られれば変更できません。
インハウスを行えば外注費の削減が可能です。委託先企業により異なりますが、アウトソーシングを活用する場合初期費用と毎月のランニングコストが発生します。また、委託内容が高度になるほど料金も高額になりがちです。

メリットがある一方で、インハウスには以下のデメリットがあります。
順に解説します。
インハウスを行うには、該当業務を担当する人材が必要です。採用や育成が求められるでしょう。ただ、専門人材の採用・育成には時間とコストがかかります。とくに、近年はDX需要が高まっている一方で専門人材の供給が追いついていません。人材を獲得できず、インハウスを行えない可能性があるでしょう。
なお、IT人材不足の状況について詳しく知りたい方は、以下もご覧ください。
⇒日本のIT人材不足の実態とは?原因や対処法、エンジニアに求められるスキルを解説
できる業務が人の量と質に左右されることも、インハウスのデメリットです。例えば、コールセンターのアウトソーシングを辞めようと思っても、対応できる人員数を確保できなければ難しいでしょう。また、マーケティングやSEOに関する知識・スキルを有する人材が居なければ、成果が出ない恐れがあります。
インハウスを行うことにより、業務負担が増加するリスクもあります。基本的に、アウトソーシングを辞めればその業務を誰かが担当しなければなりません。業務量が少なく余裕がある従業員が多かったり、新たな人材を確保できたりすれば問題ありませんが、そうでない場合には既存従業員に負荷がかかります。
インハウスの場合、人件費のコントロールが困難です。従業員として雇用すれば、閑散期や業務量が減っても賃金を支払い続けなければなりません。また、期待した成果がでなくても、雇用し続ける必要があります。

インハウスの導入ステップは以下の通りです。
ここからは、上記各ステップについて解説します。
まず、インハウスを導入するゴールや目的を明確にします。目的により、どの業務を対象とするのかやどの程度のコスト・手間をかけるかが異なるためです。
また、インハウスは業務処理手法の一つでしかありません。目的によっては、アウトソーシングし続けた方が良いケースもあります。
目的が明確になったら、対象業務といつまでにどのような状態を目指すかを定めます。また、スケジュールと実施施策も検討しましょう。
続いて、計画に基づき必要な人材やツールをそろえます。社内に適する人材がいない場合には採用が必要です。近年は、便利なツールが数多く出ていますが、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、要件を確認して自社に合うものを探しましょう。
インハウスには人材育成も必要です。高度な専門人材の採用は簡単ではありません。また、担当者が一人しかいない場合離職リスクが高まります。
セミナーへの派遣やオンラインスクールの利用などにより、人材の育成を行いましょう。また、マニュアルを作成して誰でも業務を行える体制作りが重要です。
自走できる体制が構築できたら、運用テストを行います。想定する業務が問題なく処理できるかや、成果が出るかを確認しましょう。また、導入したツールの使い勝手なども確認します。
運用テストで大きな問題がなければ、インハウスを本格導入します。また、定期的に問題がないか目的を達成できているかを確認しましょう。問題が見つかった場合には、改善策を検討・実施します。継続的にPDCAを回すことで成果が高まります。

最後に、インハウスを成功させるための以下ポイントを紹介します。
インハウスの導入時は、スモールスタートを意識しましょう。インハウスが最初から上手くいくとは限りません。スモールスタートすれば、失敗したときのリスクを減らせます。
また、人材の確保やツールの導入には多くのコストがかかります。最初から完璧を目指すとなかなか取り組みを始められないでしょう。
定期的な状況のチェックも、インハウスの成功に重要です。導入前に目標を明確にして、導入前にはKPIも定めましょう。KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、目標の達成状況を評価する定量的な指標のことです。評価するための指標がなければ、インハウスが上手くいっているか問題があるか判断できません。
ツールの活用も欠かせません。「インハウスのデメリット」の章で解説した通り、インハウスを導入すると従業員の業務負担が増加する恐れがあります。ツールを効果的に活用すれば、業務改善でき既存業務の負担を減らせます。
インハウスにこだわり過ぎないことも重要です。インハウスには、メリット・デメリットがあり、企業にとって適切な手法でないケースもあるでしょう。場合によっては、アウトソーシングした方が良い可能性もあります。

インハウスとは、企業がアウトソーシング(外部委託)せずに企業内で業務を行う(内製化)ことです。インハウスは柔軟性が高く、業務の変更などを比較的手軽に行えます。また、社内にノウハウを蓄積できるなどのメリットもあるでしょう。
一方で、人材の採用や育成が必要で、人材の量・質によりできる業務が左右されるデメリットが存在します。とくに、不足しているIT人材の採用は難しく、獲得できたとしても人件費が高い傾向があるでしょう。
インハウスはメリット・デメリット双方が存在するため、企業の目的や状況に応じた使い分けが重要です。インハウスにこだわりすぎると、体制作りに時間がかかり施策の実施が遅くなったり、質が悪くなったりする恐れがあります。
インハウスにこだわるのではなく、アウトソーシングと比較しながら使い分けを行うと良いでしょう。