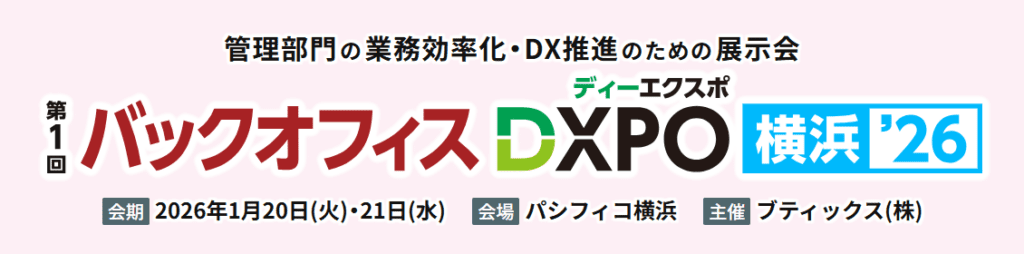
弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...

リプレースとは、システムなどを新しいものに置き換えることです。システムの安定稼働を目的に実施され、パフォーマンスの向上やセキュリティ強化、システムにおけるブラックボックス化の解消が期待できます。リプレース実施時には、詳細な要件定義を行い余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
本記事では、リプレースの概要や行う方法の種類、実施ステップと成功のポイントについて詳しく解説します。リプレースについて知りたい方、実施を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

リプレース(replace)とは、システムやサーバーなどの全部もしくは一部を新たなものに置き換えることです。「リプレイス」と表記されるケースもあり、主に以下を目的に実施されます。
システムなどは長期間利用すると経年劣化で不具合が発生します。また、データ容量が不足して動作が重くなったり、アップデートに対応できなくなったりするケースもあるため、リプレースが必要です。
ここからは以下の事項について解説します。
リプレースを行う時期に関する明確な基準はありません。ただ、国税庁が以下の耐用年数を定めているため5年以内を目安にするケースが一般的です。
ソフトウェアに関しては、メーカーが定めるサポート期限が切れたり、最新のアップデートに対応できなくなったりしたタイミングで実施すると良いでしょう。
リプレースとマイグレーションは混同されがちですが、両者は別の環境に移行するか否かが異なります。リプレースの場合、製品の一部もしくは全部を新しくしますが基本的に環境自体は変わりません。一方「移行」や「移住」などを意味するマイグレーションでは、新しいプラットフォームやOSなどに移行します。

リプレースを行う方法は以下の4つです。
ここからは、上記の各方法について解説します。
システムの構成要素や機能を一度に切り替える方法です。システムにおける問題を一気に解決でき、移行作業に関する手間やコストを抑えられます。
ただ、システムの全面停止が必要で、サービス提供や業務が停止する可能性があります。また、対象範囲が広くなり問題が見逃されやすくなるため、後々トラブルが発生するリスクもあるでしょう。
一部のみを新たなシステムに切り替える方法です。システムを分割して移行作業を行うため、全面停止を避けられます。また、一括移行方式と比較してリスク発生を軽減できるのも特徴です。
ただ、複数に分けて実施するため全体のリプレースには時間やコストがかかります。また、新旧システムの相性を考えながら実施する必要があり、入念な計画の立案が求められます。
既存のシステムと新たなものを同時稼働させて移行する方法です。システムの稼働を継続した状態でリプレースできるため、業務やサービス提供の停止を避けられます。また、同時稼働させている間に移行の問題を解決できるでしょう。
ただ、2つのシステムを稼働することになるため負担やコストが増加します。
一つの部門など影響範囲が少ない箇所でシステムの移行を行い、運用で問題がないかを確認した上で、全部門の切り替えを行う方法です。トラブルの発生を最小限にでき、事前に検証を行うためノウハウを蓄積した状態で全体のリプレースを実施可能です。
ただ、実質的にリプレースを2回行うことになり、時間と手間、コストが増加します。また、試験段階でトラブルが発生しなくても、本番環境では発生する可能性があります。

続いて、リプレースを行う以下のメリットと効果について解説します。
リプレースを行うことで、システムのパフォーマンス向上が期待できます。システムが古い場合、以下の弊害が発生します。
新しくすることにより上記の問題を解決可能です。また、パフォーマンスが向上すればAIやIoTなどの最新テクノロジーを導入でき、DXの推進が容易になります。新たな事業展開や業務効率化も期待できるでしょう。
セキュリティの強化もリプレースを実施する効果の一つです。ベンダーのサポートが終了すれば、セキュリティ上の欠陥をなくすためのアップデートが行われません。脆弱性があれば、不正アクセスやウイルス感染の原因になります。リプレースにより最新のセキュリティ対策を施せば、サイバー攻撃を受けるリスクを軽減可能です。
リプレースは、システムのブラックボックス化解消に有効です。長期間利用しているシステムは、カスタマイズが複数回行われており、内部構造が複雑でブラックボックス化しているケースが少なくありません。また、運用担当者の離職によりシステムに精通している人材がいなくなり、ブラックボックス化する場合も存在します。
ブラックボックス化すると、メンテナンスが困難になったり、セキュリティリスクが発生したりする原因になります。リプレースすることで、透明性を高めブラックボックス化を解消可能です。

パフォーマンスやセキュリティ向上に有効なリプレースですが、実施には手間・コストがかかります。また、システムやその構成・設定が複雑化し過ぎていると、内容を把握できずリプレースが予定通り進まないケースもあります。メーカー保証期限が切れる前にリプレースを完了できず、保守対応してもらえない期間でトラブルが発生すれば、業務に支障をきたす恐れもあるでしょう。
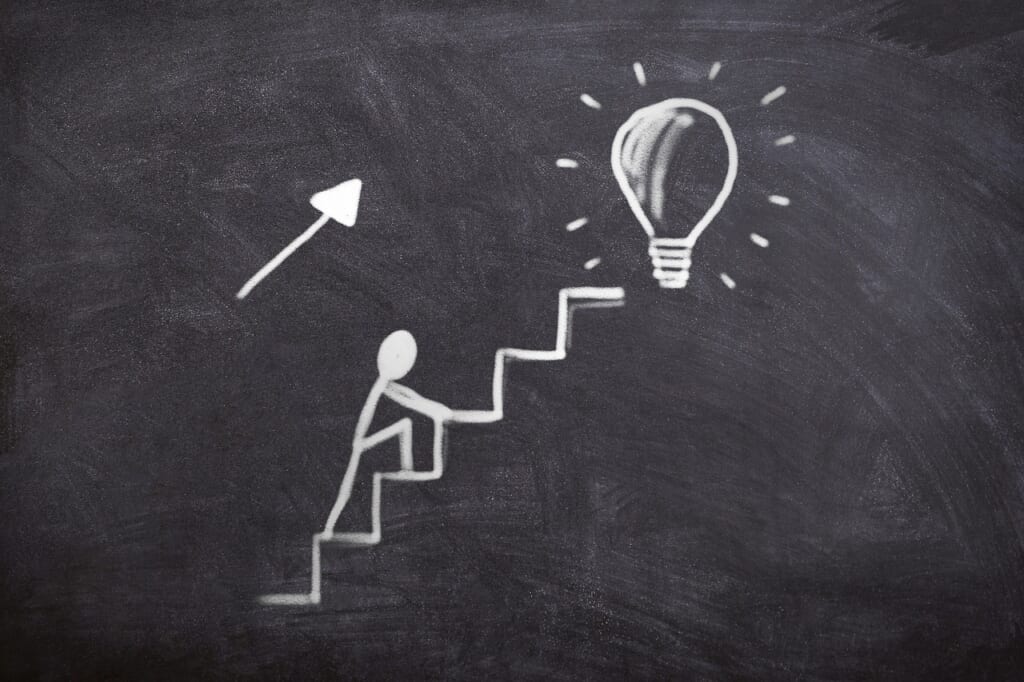
リプレースの実施ステップは以下の通りです。
順に解説します。
まずは、なにをどのように変えたいかや、そのまま残す部分などの要件を整理します。後ほど詳しく解説しますが、詳細な要件定義を行わない場合想定と異なるシステムになってしまうリスクがあるため注意しましょう。
続いて、以下を含めた詳細な計画を作成します。
上記が明確になったら社内で共有しましょう。
計画策定後に移行データの選定と準備を行います。そのままの形式でデータを移行できる場合には問題ありませんが、リプレースで仕様変更が行われるケースでは、加工や調整が必要です。
システム変更により、データが使えなくなったり破損したりすれば業務に支障をきたします。リプレース前にデータ形式の変更などが必要かを確認して、必要な場合にはしっかり準備しましょう。
続いて、リハーサルを実施しましょう。リハーサルせずにリプレースを実施すると、思わぬトラブルでデータの破損などが発生する可能性があります。事前にテストを行うことで、トラブル発生を抑えるとともにリプレース後もスムーズに通常業務を実施可能です。
リハーサル実施時には以下を確認すると良いでしょう。
リハーサルが完了したら実際にリプレースを実施します。リハーサル時には起きなかったトラブルが発生する可能性もあります。想定外の問題が起きても冷静に対処しましょう。

最後に、リプレースを成功させる以下6つのポイントを紹介します。
リプレースを成功させるためには詳細な要件定義が欠かせません。マイグレーションと異なり、リプレースの場合は現行の環境・システムが踏襲されるため、要件定義にあまり手間やコストをかけたくないと感じる人もいるでしょう。
ただ、詳しい要件定義を行わなければ想定と異なるシステムが完成してしまう恐れがあります。以下を踏まえた要件定義を行うと良いでしょう。
余裕を持ったスケジュールを組むことも重要です。少しでも早くリプレースを完了させたいと考える人も多いでしょう。ただ。余裕のないスケジュールを組むと、無謀な日程で作業しなければならずトラブル発生の原因になります。
リプレースやシステム開発では、想定外の事態が起こることも少なくありません。日程にゆとりを持たせて、問題が発生した際にも冷静に対処できるようにすると良いでしょう。
依頼するベンダーは慎重に選定しましょう。リプレースに関するサービスを提供するベンダーは数多く存在して、ベンダーごとに得意な分野などが異なります。以下を参考にベンダーを選ぶと良いでしょう。
ベンダーに丸投げしないことも重要です。リプレースを業者任せにする企業も少なくありませんが、依頼企業が主体的に関わらない場合、想定外のシステムとなる可能性があります。希望をしっかりと伝え、ベンダーと二人三脚でリプレースを進めることが重要です。
リプレース実施時にシステムを停止する場合には、その影響範囲を確認しておきましょう。対象のものだけでなく、関連するシステムに影響が出るケースもあります。事前に影響範囲を確認して対策を行わなければ、業務に支障をきたす恐れがあるでしょう。社外向けにサービス提供を行うシステムが対象の場合、ユーザーに悪影響が出れば顧客離れの原因になります。
既存システムとの連携を考慮することも必要です。リプレースにより他のシステムと連携できなくなれば、手作業で行わなければならず業務負担が増加します。また、人がデータの転記などを行った場合、ミスが発生する可能性も高まるでしょう。

リプレースとは、システムやサーバーなどの全部もしくは一部を新たなものに置き換えることです。システムが古くなれば、動作が遅くなったり故障したりする原因になります。リプレースはシステムの安定稼働を目的に実施され、パフォーマンスの向上やセキュリティ強化、システムにおけるブラックボックス化の解消が期待できます。
実施方法には、一括移行方式・段階移行方式・並行移行方式・パイロット方式があり、それぞれメリット・デメリットが異なるため、合う方法を選択すると良いでしょう。また、実施時には詳細な要件定義を行い、ベンダーと二人三脚で進めることが重要です。
弊社SMSデータテックでは、既存のシステムから弊社サービスへの移行や移行時の新たな機能開発、システム保守・管理の代行を行っています。ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。