
10月22日(水)~24日(金)に幕張メッセにて、Japan DX Week2025秋が開催されました🍂 今回も弊社SMSデータテック...

業務属人化の解消には、業務・フローの見える化や情報共有を促進する体制の整備、マニュアルの作成など複数の方法が存在します。まずは、属人化の原因や具体的な業務を把握して、適切な対策を実施すると良いでしょう。また、優先順位付けや継続的に取り組むことも重要です。
本記事では、業務属人化の概要や解消するメリットと方法、解消する際のポイントについて詳しく解説します。属人化を解消する方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

業務の属人化とは、特定の業務や作業における処理方法などを一部の従業員しか知らない・できない状態のことです。例えば以下の現象が該当します。
業務が属人化した場合、以下のリスクやデメリットがあります。
順に解説します。
属人化は業務が滞る原因になります。標準化されていない業務は担当者しかできないため、担当する従業員が休んだり、多忙だったりする場合その業務が進みません。また、特定の従業員が離職すれば業務自体ができなくなってしまう恐れもあります。
ノウハウが蓄積されないこともデメリットの一つです。属人化している業務から得られるノウハウやナレッジは、その業務を担当する従業員しか得られません。企業の財産にはならず、担当者が退職すればそのノウハウは失われるでしょう。
属人化している業務は、本人しかわからないため品質の安定化や管理もできません。ミスが発生しても、気付くのが遅れ後々大きなトラブルに発展する恐れがあるでしょう。また、営業の場合顧客へのアプローチ方法が異なれば、満足度の低下につながるリスクもあります。
属人化は業務改善の妨げにもなります。処理方法や手順を特定の担当者しか知らなければ、その方法が最適かの評価ができません。問題点に気付くことができず、非効率な業務処理が行われ続ける可能性もあるでしょう。
特定の従業員に負荷がかかる点も属人化のデメリットです。業務量や負荷状況を管理職が把握できず、同僚もフォローできません。長時間労働や業務の遅れが発生する原因になるでしょう。また、人事評価において適切な評価も困難です。

続いて、業務が属人化する代表的な以下5つの原因について解説します。
高い専門性を求められる場合、業務が属人化する原因になります。特殊なスキルや専門的な知識を有する人材は少なく、そもそも実施できる人材自体が多くありません。また、マニュアル化が困難なケースも多くあります。専門性を身に付けた人材の育成にも多くの時間とコストがかかるため、後回しにされがちです。
業務が可視化されていないことも、属人化を引き起こす原因の一つです。業務の流れや処理方法が、特定の従業員しかわからない状態になっていれば、他の人はなにが行われているかを把握できません。その結果業務の属人化につながります。
情報共有する体制や仕組みが未整備の場合も、属人化を招きます。具体的には、ワークフローシステムやコミュニケーションツールが未導入だったり、マニュアル化されていなかったりするケースが該当します。また、従業員が自分の優位性を確保する目的で、情報共有に消極的になっている場合もあるでしょう。
コミュニケーション不足が原因で、業務が属人化するケースもあります。コミュニケーションが少ない場合、情報共有が行われません。各人が独自の方法で実務を行う原因になり、属人化につながります。
マニュアルが存在しなければ業務の属人化が起こります。マニュアルなどの資料がない場合、業務の引継ぎや指導は口頭で行わなければなりません。ただ、従業員が日々の業務で忙しい場合、手順ややり方を教える時間の確保が難しく特定の担当者しか処理できなくなります。
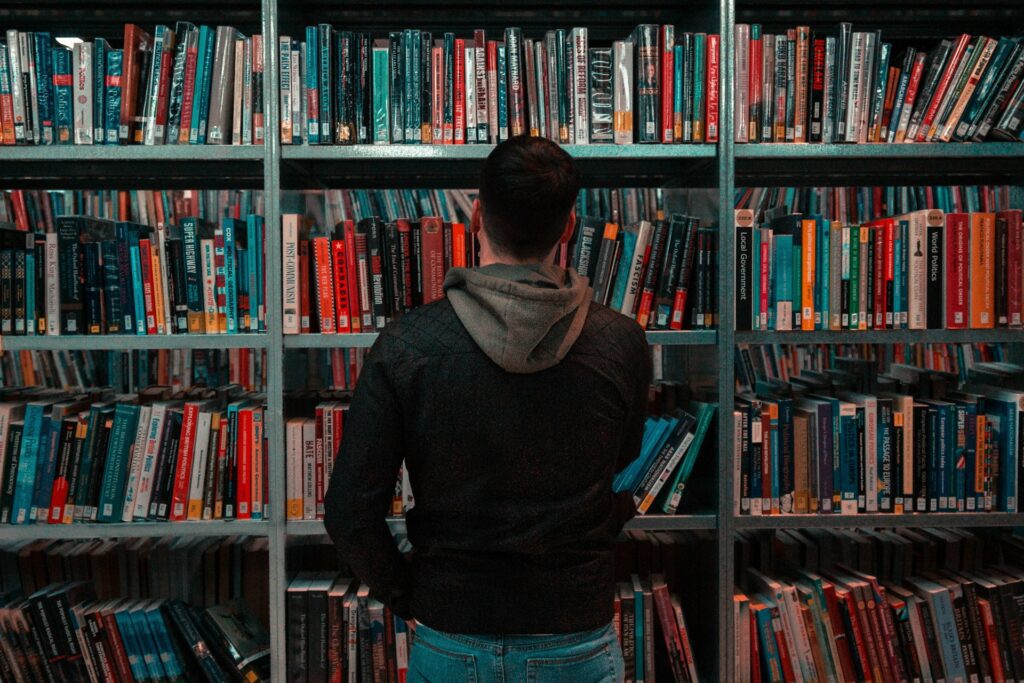
業務の属人化を解消する4つのメリットは以下の通りです。
順に解説します。
属人化を解消すれば業務効率化を図りやすくなります。多数の従業員が業務に携わるため、課題や効率化のポイントを見つけやすくなるでしょう。また、1人では思いつかない効率化のアイディアが生まれるケースもあるでしょう。
品質の安定化・向上も属人化を解消するメリットです。担当した従業員以外が、適切に業務が行われているかのチェックが可能になり、問題やミスの発見・解消ができるでしょう。
属人化の解消でノウハウやナレッジを蓄積でき、担当者が退職しても業務の継続が可能です。また、引継ぎをしやすい体制整備にもつながります。
属人化の解消は従業員が働きやすい環境の整備にも有効です。複数の従業員が特定の業務処理を可能な状態にすることで、担当者が忙しい際にフォローできるようになります。従業員の負担を分散できるでしょう。

業務の属人化を解消する主な方法は以下の5つです。
順に解説します。
業務の標準化に向け、業務やフローの見える化を行いましょう。「誰が」「いつ」「なにをしているか」の棚卸しを行い、フロー図を作成すると効果的です。図としてわかりやすく視覚化することで、属人化している業務の発見や各業務でなにをすれば良いかが明確になります。また、ボトルネックの発見や業務改善もしやすくなるでしょう。
ツールや会議体を整備して、情報共有を促進するのも良いでしょう。情報共有は、業務のやり方などノウハウ共有にもつながります。また、各従業員が有するノウハウ共有を評価する仕組みを作れば、積極的に情報をシェアする風土の醸成が期待できます。
コミュニケーションの活性化も属人化の解消に効果的です。報連相の徹底や雑談しやすい雰囲気作りで、従業員のコミュニケーションを促進しましょう。また、社内ポータルサイトの構築も有効です。
社内ポータルサイトとは、社内にある情報やアプリケーションにアクセスする際の入り口となるWebサイトのことです。コミュニケーションの活性化だけでなく、社内に散らばった情報へのスムーズなアクセスも可能になります。
社内ポータルサイトの詳細は以下をご覧ください。
⇒社内ポータルサイトとは?おすすめの作成ツール6選や導入メリットと構築のポイントを解説
マニュアルの作成も推進しましょう。マニュアルや業務手順書などの資料を作成することで、情報共有しやすくなります。
マニュアルを作成する際には専門用語の使用を避け、知識がない人も理解できるようにすることが重要です。コツや注意点などを含め、可能な限り具体的かつ詳しく記載しましょう。
誰でも実施しやすくすれば業務の属人化を解消できます。業務を見直し、誰でもできるように簡素化を図りましょう。また、ツールの導入も有効です。一部の業務を自動化・効率化することで、属人化の解消だけでなく生産性の向上も期待できます。
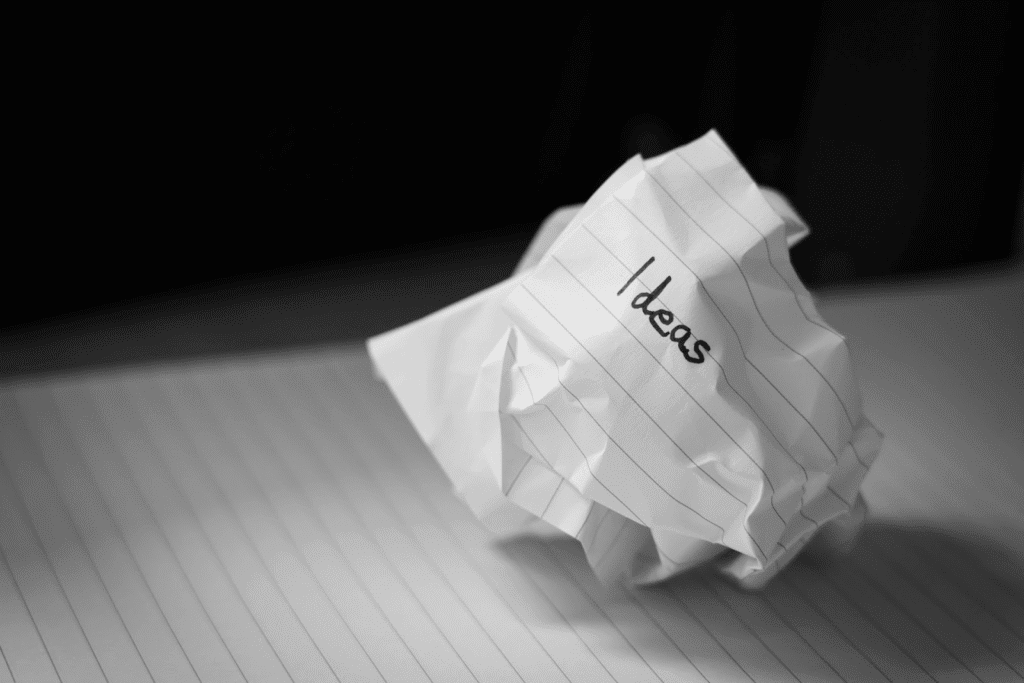
最後に、業務の属人化を解消する際の以下ポイントを紹介します。
企業内には複数の業務が存在して、全ての業務における属人化を一度に解決するのは困難です。属人化の解消に取り組む際には、優先順位を付けて取り組むと良いでしょう。
まずは業務の棚卸しを行い、コア業務とノンコア業務に分類します。企業の売上増加やコスト削減に直結するコア業務は専門性が高く定型化しにくいため、ルーティンワークであるノンコア業務から取り組むのがおすすめです。
継続的に取り組むことも欠かせません。業務処理方法やフローは、担当者の変更や新たなシステムの導入などにより変化します。また、業務効率化や品質向上を目的にフローの改善などが行われるケースもあるでしょう。
業務変更に併せてマニュアルを更新するなど、継続的に取り組まなければ一度標準化しても再度属人化します。定期的に属人化解消に向けた会議を設定するなどの取り組みも効果的です。
ツールを有効活用するのも良いでしょう。近年は、業務の属人化解消に役立つツールが多数開発・提供されています。具体的には、ナレッジマネジメントを実現するツールが挙げられます。ナレッジマネジメントとは、各個人が保有する知識やスキルを企業・組織で共有して活用する経営手法のことです。ナレッジマネジメントツールを導入すれば、ノウハウの蓄積や共有がしやすくなるでしょう。検索機能が優れているツールも多く、必要なときに目的の情報を迅速に見つけられます。
なお、ナレッジマネジメントの詳細は以下をご覧ください。
⇒ナレッジマネジメントとは?実施するメリットや導入フロー、成功させるポイントを解説

業務の属人化とは、特定の業務や作業における処理方法などを一部の従業員しか知らない・できない状態のことです。属人化した場合、業務が滞る、ノウハウが蓄積されない、品質の安定化・管理が難しいなどさまざまなデメリットが発生します。解消には、業務・フローの見える化や情報共有を促進する体制の整備、マニュアルの作成などが有効です。また、フローを見える化したりナレッジを蓄積したりするツールを用いるのも良いでしょう。
具体的には、業務プロセス・ワークフローを見える化して自動化・効率化するためのクラウド型プラットフォーム「ServiceNow」の導入がおすすめです。「ServiceNow」を利用すれば、業務のシームレス化や効率化、品質改善も実現できます。弊社SMSデータテックでは、「ServiceNow」の導入開発・保守運用をサポートしています。ご興味がある方は、以下をご覧ください。
⇒ServiceNow導入・開発・保守運用