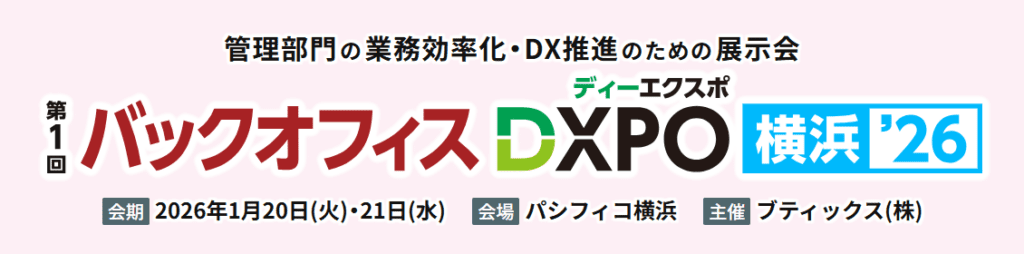
弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...

問い合わせ対応の効率化には、オペレーターのサポートや問い合わせ自体を減らす取り組み、ツールの利用などが有効です。具体的には、マニュアルの整備やFAQページの充実化、チャットボットの利用などが該当します。また、アウトソーシングを利用するのも良いでしょう。
本記事では、問い合わせ対応業務が重要な理由と課題や効率化する8つの方法、おすすめのチャットボット6選について詳しく解説します。問い合わせ対応業務を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次

問い合わせ対応とは、ユーザーから寄せられる質問や要望、クレームなどに対応することです。大きく以下の2つに分けられます。
ここからは、上記について解説します。
社外からの問い合わせ対応とは、商品・サービスの利用者や取引先からの質問などに対応することです。具体的には以下の5つが挙げられます。
多くの企業では、営業担当者やコールセンター、カスタマーサポートなどが上記に対応しています。商品やサービスに関する質問がメインですが、中には要望・クレームも存在するため、迅速な対応が求められます。
社内からの問い合わせ対応とは、従業員から寄せられる質問や要望などへの対応のことです。例えば以下の4つが該当します。
社内からの問い合わせの場合、制度やシステムの使い方に関するものがメインです。従業員が多い場合、システムに関する多数の質問が寄せられシステム担当者の負担を増加させる原因になっています。中には、社内からの問い合わせも外部に委託する企業が存在します。

問い合わせ対応には、迅速かつ丁寧な対応が求められます。ここからは、問い合わせ対応が重要な以下4つの理由について解説します。
問い合わせ対応は、顧客や従業員の満足度に影響を与えます。顧客からの問い合わせに素早く対応すれば、信頼やロイヤリティが向上して、長期間商品・サービスを利用してくれる可能性が高まります。一方、何日も返信しない場合顧客からの信用を失うでしょう。
また、従業員の問い合わせに返答しなければ、モチベーションが下がる原因になります。業務が滞ってしまうケースもあるでしょう。素早く返答すれば、従業員のモチベーションが高まりストレスも軽減されます。
商品・サービスの改善に役立つ点も、問い合わせ対応が重要な理由です。問い合わせ窓口には、顧客からの感想も集まります。また、質問やクレーム・要望を分析することで、商品・サービスを改善する際のアイディアも得られるでしょう。新たなビジネスの創出につながる可能性もあります。
問い合わせ対応は、他社との差別化要因にもなります。多くの企業が研究を重ね魅力的な商品・サービスを提供しています。高性能・高品質なものが多く、商品やサービスで他社と差別化することは簡単ではありません。
問い合わせ対応やアフターサポートの重要性が増しています。迅速で丁寧な回答は企業の付加価値になるでしょう。
問い合わせ対応は、売上に影響を与える要素の一つです。顧客満足度が高まれば、クロスセルやアップセルの創出につながります。クロスセルとは関連する別の商品も一緒に購入してもらうことで、アップセルとはより高単価の商品やプランを購入してもらうことです。
また、長期間利用してもらえる可能性も高まるため、LTVを最大化できます。LTV(顧客生涯価値)とは、顧客と取引を始めてから終わるまでにもたらされる利益や価値を示す指標のことです。

重要な問い合わせ対応ですが、以下の課題を抱える企業が少なくありません。
ここからは、上記それぞれの課題について解説します。
問い合わせ対応業務を担当するオペレーターの経験やスキルの差により、回答内容・品質にバラツキが発生するケースがあります。近年は、個人がSNSなどを活用して自分の体験などを発信しやすくなっているため、自分への対応と他者への対応を比較して不満を抱く方がいるでしょう。
また、例え経験が浅いオペレーターが回答したとしても、ユーザーからすれば企業の回答です。品質が悪ければ、企業への不信感につながる恐れがあるでしょう。
対応に時間がかかることも、問い合わせ対応業務における課題です。特に、高度な内容の質問が寄せられれば、多数の部署に確認が必要となり回答に時間がかかります。回答が得られるまでに時間がかかった場合、多くのユーザーは不満を抱くでしょう。
問い合わせに対応しきれないケースもあるでしょう。問い合わせ件数が多かったり、オペレーターが少なかったりすれば、顧客が電話をしてもつながりません。ユーザーは電話がつながるまで待つ必要があり、長時間かかる場合にはストレスを感じるでしょう。
オペレーターにも負担がかかり、離職の原因になります。オペレーターが少なくなれば、一人あたりが対応する問い合わせ件数が増加して負担が増える悪循環に陥ります。
情報共有できていないことも、問い合わせ対応業務における課題の一つです。全体で情報共有ができていない場合、回答内容や品質にバラツキが生じる原因になります。また、回答したかどうかが不明になり、抜け漏れが発生するリスクもあるでしょう。
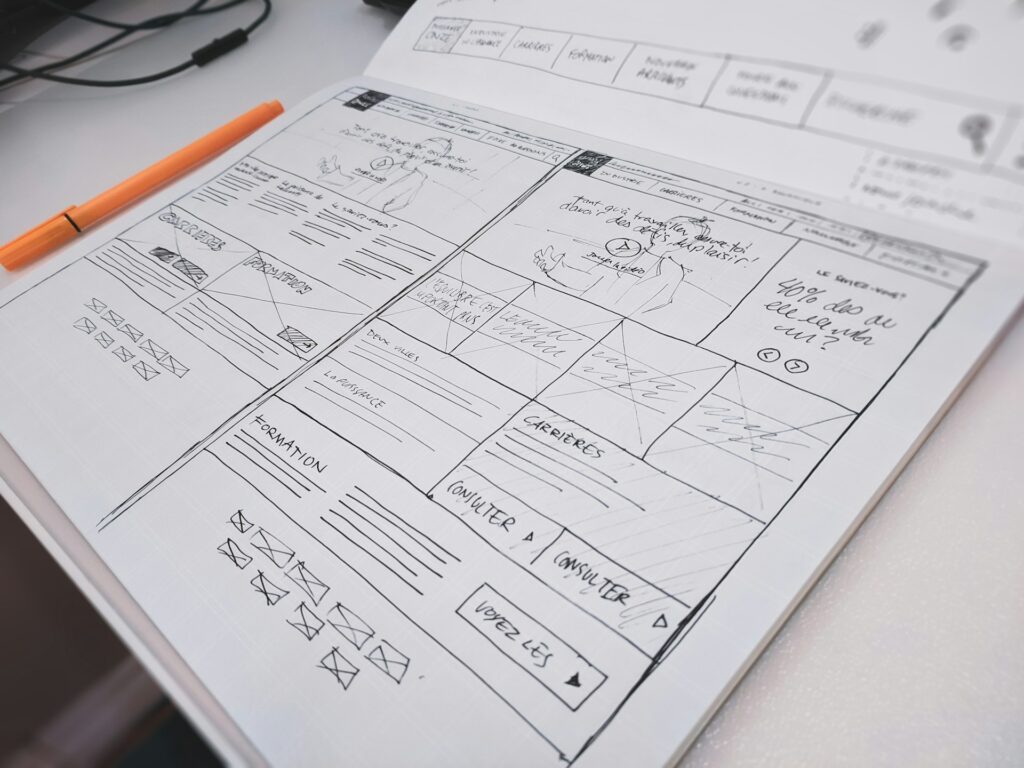
問い合わせ対応を効率化するには以下8つの方法が有効です。
順に解説します。
マニュアルを整備することにより、問い合わせ対応を効率化できます。マニュアルがあれば、経験が浅くても質問に対してどのような回答をすれば良いかすぐにわかるでしょう。また、回答内容や品質のバラツキを抑えられます。さらに、マニュアルを整備する過程で業務や回答を見直す機会になり、改善点を見つけられるケースもあります。
問い合わせ対応の効率化には、返信用のテンプレート整備も効果的です。似た質問が多数寄せられる場合には、返信用のテンプレートを作成すると良いでしょう。メールやチャットで毎回テキストを入力する手間を減らせます。
従業員の教育を定期的に実施するのも効果的です。マニュアルがあったとしても、オペレーターのスキルや経験により多少の差が発生します。従業員を教育してレベルを高めることで、オペレーターの水準が向上します。顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
FAQの充実も問い合わせ対応効率化に有効です。問い合わせ頻度が高い質問をFAQページにまとめれば、ユーザーの自己解決率が高まり問い合わせ自体を減らせます。FAQページはわかりやすい場所に設置して、検索機能の実装などによりユーザーの疑問を解決しやすい体制を整えましょう。
オンボーディングの実施も有効です。オンボーディングには以下の2種類が存在します。
オンボーディングで従業員や顧客に対して教育を行い不明点を解決すれば、問い合わせ件数を減らせます。また、満足度も高まるでしょう。
なお、オンボーディングの詳細は以下をご覧ください。
⇒SaaSビジネスのオンボーディングとは?実施ステップや成功のポイントを解説
チャットボットなどのツール利用も良いでしょう。ユーザーからの質問に対して自動で回答するチャットボットやAIを活用すれば、問い合わせ対応業務を効率化できます。全てをチャットボットで対応するのではなく、高度な質問に対してはオペレーターが対応する体制を整備している企業も多く存在します。
自社で問い合わせ対応が難しい場合には、業務をアウトソーシングすることもおすすめです。サポートデスクやコールセンター業務を自社で用意しようとすれば、場所・設備の用意やオペレーターの教育など、多くの手間・コストがかかります。アウトソーシングすれば、業務の効率化だけでなく迅速な問い合わせ対応体制の整備が実現するでしょう。また、近年はシステム担当者の確保が難しいため、問い合わせ対応を含むシステム関連業務をアウトソーシングする企業も少なくありません。
なお、アウトソーシングの詳細は以下をご覧ください。
⇒アウトソーシングとは?メリット・デメリットもわかりやすく解説
⇒おすすめのアウトソーシング企業7選!概要やメリット・デメリットも解説
問い合わせ対応の一元管理も業務の効率化に役立ちます。電話やメール、問い合わせフォーム利用など、複数の経路が用意されている場合、オペレーターはさまざまな画面を確認しなければなりません。手間がかかるとともに、抜け漏れが発生するリスクが生じます。また、管理者も対応済みかの確認やフォローがしにくいでしょう。

最後に、問い合わせ対応の効率化に役立つおすすめの以下チャットボット6選を紹介します。
なお、チャットボットの詳細や他のチャットボットについて知りたい方は、以下もご覧ください。
⇒おすすめのチャットボット18選!種類やメリット・デメリット、比較のポイントも解説

Chat Plusは、2万件を超える導入実績を持つAIチャットボットです。「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」のチャットシステム部門では、以下の4部門でNo.1に選出されました。
プランが複数用意されているため、自社に合うものを利用可能です。
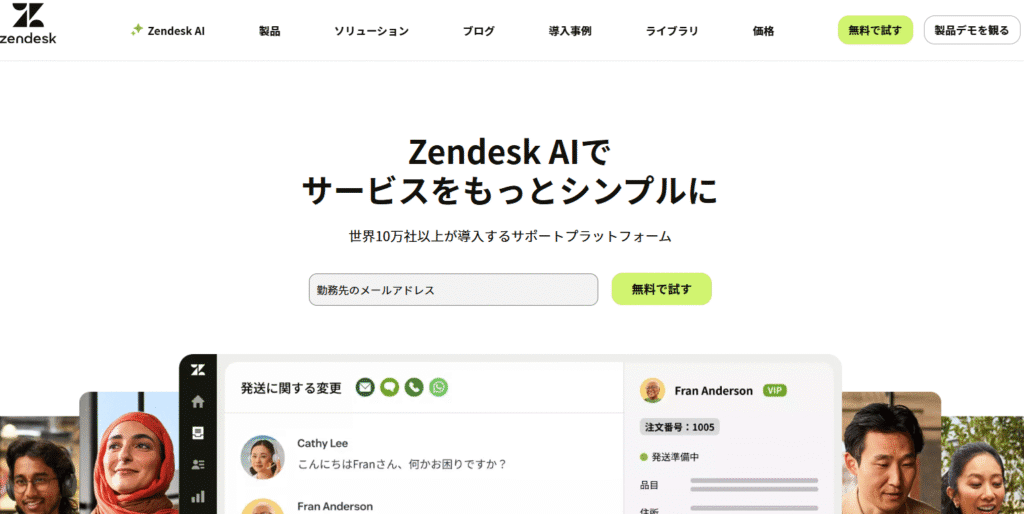
Zendeskは、世界で10万社以上が導入しているサポートプラットフォームです。あらゆるチャネルからの問い合わせを一元化でき、抜け漏れの発生を防止可能です。また、AIエージェントが搭載されているため、複雑な問題への回答も自動化できます。

PecoChatは、ファイルのアップロードなどにより容易に導入できるチャットボットです。導入・利用にあたり、手間のかかる設定や高度な専門知識は必要ありません。有人対応への切り替え機能も実装されており、高度な質問が寄せられた際も安心です。

FirstContactは、業界最安値水準の2,980円から利用できるチャットボットです。既存のマニュアルやFAQを基に、高精度な回答生成を行ってくれます。また、LINEやChatwork、Slackなど連携できる外部ツールも豊富です。

PKSHA Chatbotは、Webサイトに数行のタグを埋め込むだけで簡単に導入できるチャット型対話エンジンです。ビッグデータを活用した辞書データを搭載しており、日本語に高精度で対応可能です。また、専門的な知識やスキルがなくても問い合わせ内容を分析でき、対話性能の向上が図れます。
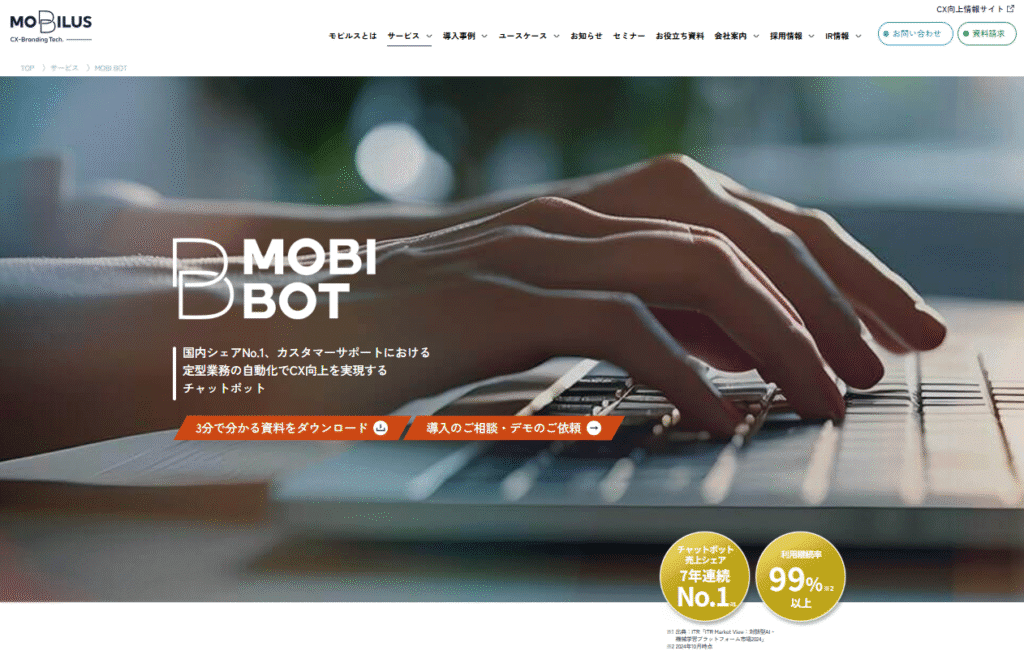
MOBI BOTは、問い合わせ対応だけでなく手続き処理も自動化できるチャットボットです。基幹システムとの連携が可能で、本人確認や顧客情報の参照・変更、注文などの自動化に役立ちます。大手企業を中心に、金融・メーカーから自治体まで幅広い業種で利用されています。

問い合わせ対応は、満足度や売上に影響を与え、他社との差別化に役立つ重要な業務です。ただ「回答内容や品質にバラツキがある」「対応に時間がかかる」「対応しきれない」などの課題を抱える企業も少なくありません。