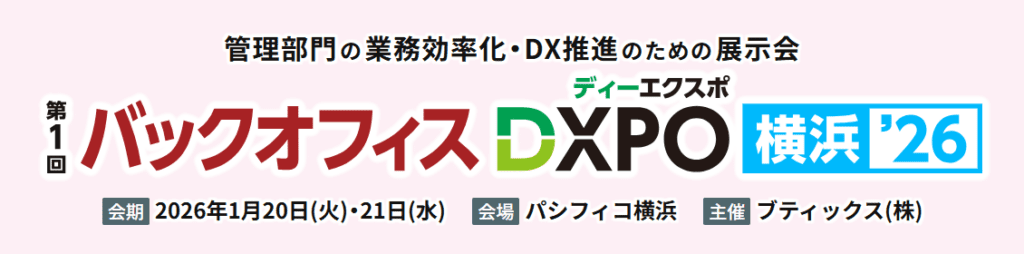
弊社SMSデータテックは、2026年1月20日(火)~21日(水)の2日間、パシフィコ横浜にて開催されるバックオフィスDXPO横浜’2...
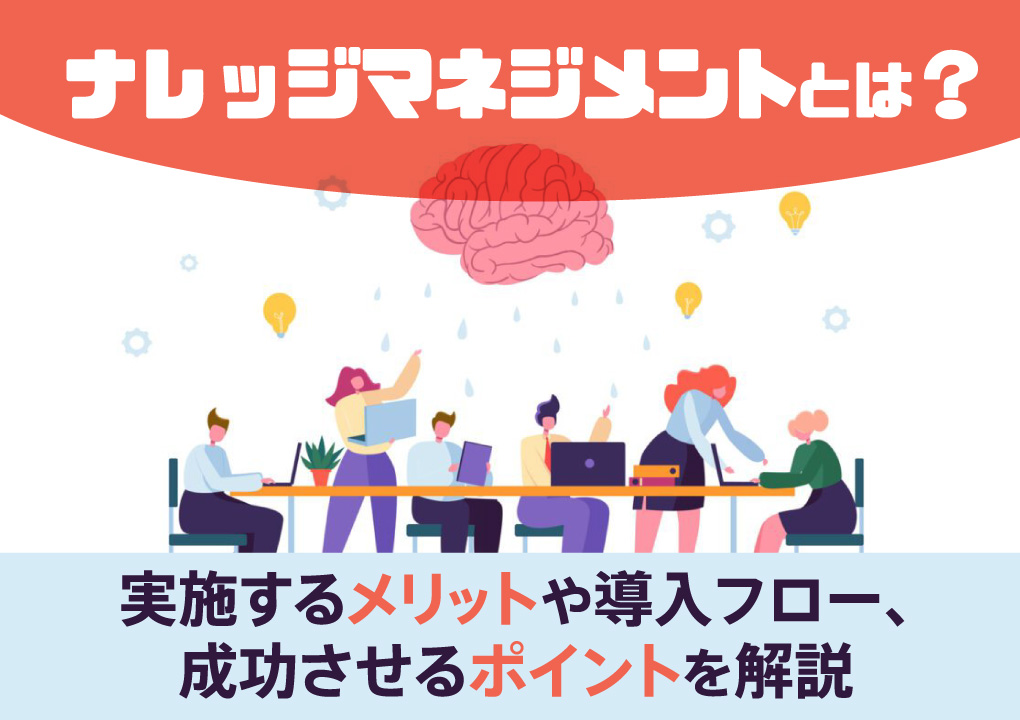
ナレッジマネジメントとは、企業・組織に属する各個人が保有しているノウハウを体系化・活用する手法のことです。終身雇用制度の崩壊により長期的な従業員の育成が困難で、かつ企業競争の激化により従業員の早期戦力化が必要になったため注目を集めています。
本記事では、ナレッジマネジメントの概要や実施するメリット、導入フローについて詳しく解説します。ナレッジマネジメントについて知りたい方、導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
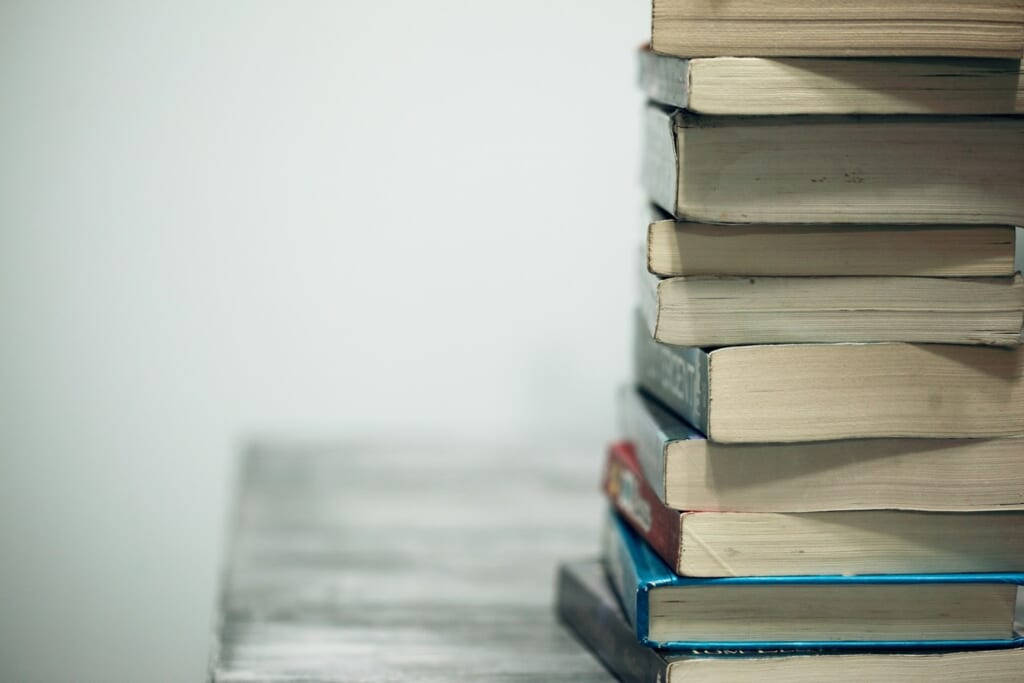
ナレッジマネジメントとは、各個人が保有する知識やスキルを企業・組織で共有して活用する経営手法のことです。1990年代に一橋大学大学院の野中郁次郎教授らが提唱した「知識経営」が基になったといわれています。
ここからは、以下の事項について解説します。
ナレッジマネジメントが注目されている背景には、終身雇用制度の崩壊による知識・スキル伝承の難易度向上が関係しています。従来、日本の企業では終身雇用制度を前提として、長期間かけ従業員の育成を行っていました。ただ、終身雇用制度が崩壊したため知識やスキル、ノウハウの承継が困難になっています。
また、グローバル化や消費者ニーズの多様化など企業を取り巻く環境は厳しくなっており、従業員を効果的に育成しなければ企業が衰退してしまうでしょう。ナレッジマネジメントを行うことで、従業員や組織力の強化を図り企業競争力の向上を行うことが求められています。
以前のナレッジマネジメントは紙をベースに行われており、目的とする情報を探すのに時間がかかっていました。また、情報が重複したり更新されなかったりする課題も存在しました。近年では、ナレッジマネジメントを行う専用のツールが開発・提供され、クラウド上で情報共有する手法が一般的になっています。テクノロジーの進歩により、大量のデータであっても迅速かつ容易な共有・利用が可能になりました。
ナレッジマネジメントの種類は大きく以下4つに分けられます。
順に解説します。
優秀な従業員のノウハウや行動、考え方を共有するタイプです。成果を上げている従業員のノウハウを基にするため、組織全体のスキル向上が期待できます。
社内に分散している情報を集約するタイプです。埋もれているノウハウを活用できる形式になることで、企業の競争力強化や付加価値の向上を実現できます。
企業内外の専門的な知識をデータベース化して共有・活用するタイプです。例えば、よくある質問をFAQにまとめておくことで自己解決が図れるようになり、業務効率化につながります。
顧客に関する情報を共有するタイプです。スムーズな顧客対応の実現や満足度向上の向上、トラブルの回避が期待できます。

続いて、ナレッジマネジメントを実践する以下4つのメリットについて解説します。
ナレッジマネジメントの導入により、人材や組織力の強化が図れます。優秀な従業員の考え方や行動を真似れば、各個人の成果が向上するでしょう。顧客満足度も高まります。
業務効率化にもナレッジマネジメントは有効です。ノウハウが体系化されていれば、新入社員であっても早期に業務習得できるでしょう。また、生産性の高い行動を体系化すれば従業員の無駄な行動が減少します。
人材育成の最適化も、ナレッジマネジメントを導入するメリットの一つです。自己学習が可能な形にナレッジが体系化されていれば、教育の時間を減らせるでしょう。不明点のみ質疑応答で対応すれば良いため、教育者・被教育者ともに効率が高まります。また、どのような教育をすれば良いかも明確になるでしょう。
ナレッジマネジメントの導入は、属人化の防止にもつながり特定の個人に依存しない業務運営が可能です。属人化は、業務が滞ったり特定の個人に負担がかかったりする原因になります。ナレッジマネジメントの導入により、複数の人が同程度のクオリティで業務ができるようになるでしょう。
なお、属人化解消のメリットや解消する方法の詳細を知りたい方は以下もご覧ください。
⇒業務の属人化を解消する方法とは?属人化の原因や解消するメリットも解説

ナレッジマネジメントの推進には「SECIモデル」の活用が有効です。SECIモデルとは、言語化されていない「暗黙知」を客観的な知識である「形式知」に変換・転移するとともに、新たな暗黙知を生み出すサイクルのことです。
ここからは、以下の事項について解説します。
SECIモデルは以下4つのプロセスにおける頭文字を取り名付けられました。
順に解説します。
共通の体験を通じて暗黙知を伝えるプロセスです。具体的には、OJTやロールプレイング、営業同行が該当します。
獲得した暗黙知を形式知に変換するプロセスです。複数人で話し合いながら、映像や図などを活用してわかりやすいマニュアル・報告書にまとめます。
形式知の組み合わせにより新しい知識やアイディアを創造するプロセスです。表出化で生み出された形式知を整理・連結させ、体系的で総合的な知識に昇華させます。
形式知を実践することにより、新たな暗黙知を獲得するプロセスです。体系化された知識を行動に移すことにより、新たな知識・スキル・ノウハウを得られます。
SECIモデルでは、暗黙知を形式知に変換する過程でそれぞれのプロセスに合わせた以下の「場」が必要です。
順に解説します。
個人の体験や考え方を共有する場です。OJT・ロールプレイング以外に、雑談やランチ会、飲み会も創発の場に該当します。
暗黙知を言語化する場です。複数人で話し合うミーティングやディスカッション、ブレインストーミングなどが該当します。
形式知の整理と組み合わせが行われる場です。Excelや専門システムにノウハウを集約して、それに基づくディスカッションを行うと効果的です。
形式知を実践することで新たな暗黙知を得る場です。実際の業務だけでなく、研修やシミュレーションも該当します。

ナレッジマネジメントを導入するフローは以下の通りです。
順に解説します。
まずは、ナレッジマネジメントを導入する目的を明確にしましょう。目的を明確にすれば、最適な手法や集約・蓄積する情報が明らかになります。また、目的を共有することにより従業員からの協力も得やすくなります。
目的を基に、どのような情報の集約・蓄積が必要かを検討します。ナレッジマネジメントには時間や手間がかかるため、優先順位を付けて取り組むことが重要です。どのようなナレッジがあり、どの情報共有が目的達成・成果に直結するかを検討しながら選定すると良いでしょう。
続いて、ナレッジマネジメントを実践する方法の検討を行います。ナレッジマネジメントはExcelか専門システムの活用により実施することが一般的です。方法が決まったら、実際に情報の集約を行いましょう。
ExcelをはじめとするMicrosoft office製品であれば、多くの企業が利用しているため追加のコストをかけずに実施できます。また、利用者が多く操作方法を新たに覚える必要もないでしょう。ただ、共同編集できない、目的とする情報が探しにくいなどの課題も存在します。
近年はナレッジマネジメントに特化したシステムが数多く開発・提供されています。コストがかかる一方で、検索や分析機能などが充実しており効率的なナレッジマネジメントが期待できます。本格的なナレッジマネジメントに取り組みたい企業には、システムの活用がおすすめです。
ナレッジマネジメントは、知識やスキルを集約しても活用されなければ意味がありません。定期的に利用状況の調査や従業員へのアンケートを実施して、その結果を基に改善を行いましょう。また、より良いノウハウが生み出された際には更新することが重要です。

最後に、ナレッジマネジメントを成功させる以下3つのポイントを紹介します。
ナレッジマネジメントの実施には、従業員の理解が欠かせません。特に、多くのナレッジを保有する優秀な従業員は多忙な人が多く、情報提供に時間を割けなかったり自分のノウハウを他人に共有することに抵抗を覚えたりする人もいるでしょう。ただ、従業員からの協力を得られなければ最適なナレッジの蓄積が困難です。従業員が前向きに協力したくなる体制の構築が必要です。
情報を共有しやすい体制を整えることも重要です。ノウハウの登録や利用に手間がかかれば、ナレッジマネジメントが形骸化してしまいます。容易に情報共有可能な体制を整備すれば、活発な情報登録や利用が期待できます。
ナレッジマネジメントが推進されると、全てマニュアルを基にした業務処理が行われるケースがあります。業務の正確性や処理スピードの向上が見込まれる一方で、自ら考えて行動する従業員が減少するため併せて思考の重要性を伝えることも重要です。マニュアルを基にした行動は、従業員の自主性やモチベーション低下の原因になります。また、最適な業務処理方法は状況により異なるため、従業員が考え工夫してナレッジを改善することも必要です。

ナレッジマネジメントとは、各個人が保有する知識やスキルを企業・組織で共有して活用する経営手法のことです。終身雇用制度の崩壊により長期的な従業員の育成が困難で、かつ企業競争の激化により従業員の早期戦力化が必要になったため注目を集めています。導入すれば、人材・組織力の強化や業務効率化、属人化の防止などが期待できます。
ナレッジマネジメントの導入時には、まず目的を明確にして情報の整理と選定を行いましょう。企業・組織には多くのナレッジが眠っているため、優先順位を付け取り組むことが重要です。
また、全てを自社で完結させるのでなく、外部パートナーを上手く使うのも良いでしょう。ノンコア業務はナレッジマネジメントの対象にせず、アウトソーシングするのもおすすめです。