
2026年3月11日(水)に製造業向けのDX推進に関する共催セミナーを開催いたします! という課題を抱える方も多いのではないでしょうか...
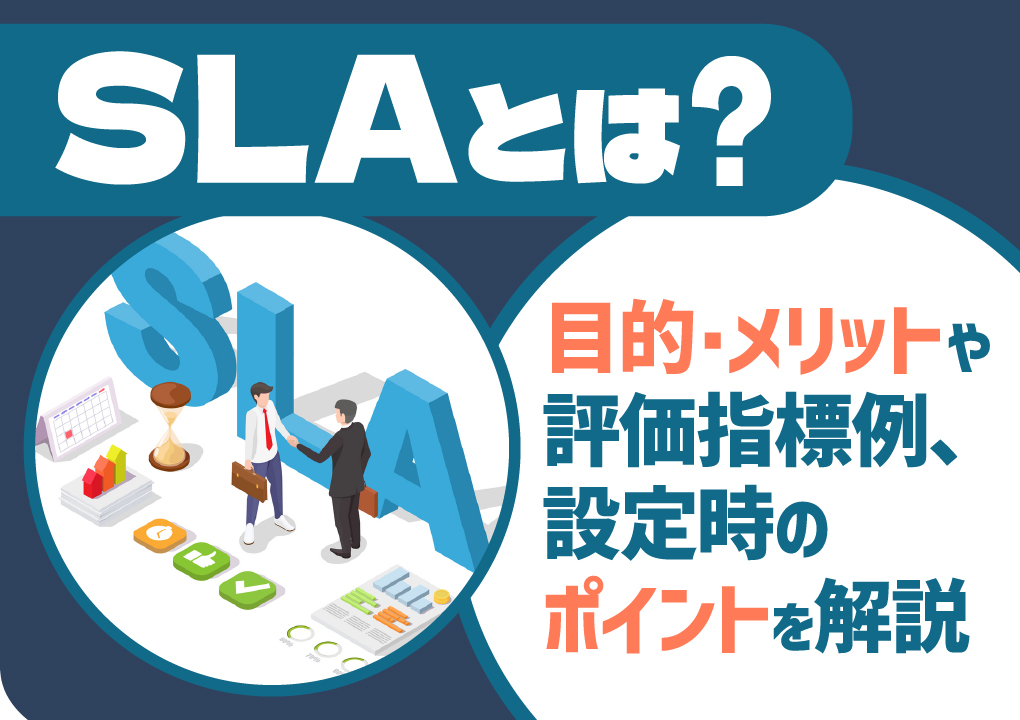
企業が提供するサービスや製品の品質を一定に保つ上で、SLA(Service Level Agreement/サービス品質保証契約)は欠かせません。SLAを適切に設定・運用すれば、提供者と利用者の双方がサービスレベルを明確に認識し、トラブルを未然に防止できます。本記事では、SLAの基本的な目的や導入によるメリット、評価指標の例、そして設定時に注意すべきポイントまでを解説します。
目次

SLAとは、サービス提供者と利用者との間で合意される「サービス品質に関する取り決め」です。提供されるサービスの内容や対応時間、可用性、障害時の対応など、具体的な基準を明文化して、信頼関係の構築と安定運用を支える役割を担います。ここでは、SLAが注目されるようになった背景や主な種類、混同されやすいSLOとの違いについて解説します。
SLAが広く採用されるようになった背景には、ITサービスの多様化とユーザー側の品質要求の高まりがあります。特にクラウドサービスやSaaSの普及により、可用性・応答時間・障害対応など、目に見えないサービス品質を契約で明示する必要性が強まりました。また、ITILやISO/IEC 20000などの国際的なITサービス管理フレームワークでも、SLAの重要性が強調されており、アウトソーシングや運用委託が一般化するなかで、提供範囲や責任を明確にするための基盤として定着しています。
SLAはおもに以下の3種類に分けられます。
ここでは、上記の種類について解説します。
「カスタマーレベルSLA」とは、ある特定の顧客との間で結ばれるSLAの形式で、その顧客が利用するすべてのサービスを対象に、品質や応答時間などを包括的に定めるものです。サービス提供者がその顧客に対して提供する義務・責任・サポート範囲を明確にするため、顧客固有のニーズに応じたSLAを設計するのが特徴です。
「サービスレベルSLA」は、特定のサービスに焦点をあて、そのサービスを利用する複数の顧客を対象に、提供される品質や可用性、対応時間などの基準をあらかじめ定めた合意書を指します。顧客ごとの個別要件ではなく、サービスそのものの標準水準を設定し、サービス提供者がその基準を満たすことを約束する形式です。
マルチレベルSLAとは、一つのSLA契約を複数のレベルに分け、それぞれ異なる対象や条件に適用する形式のサービスレベル合意書です。すべてのユーザーに共通の基準を設けつつ、特定の顧客やサービスには追加の条件や優先度を持たせるなど、「共通性」と「柔軟性」を兼ね備える運用ができるのが特徴です。
SLAとSLOは似た用語ですが、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | SLA | SLO |
| 性質 | 利用者との合意契約 | 内部目標 |
| 対象 | 総合的な要件 | 特定の指標 |
| 違反時の影響 | 未達はペナルティがある場合が多い | 未達自体は内部管理上の問題であるため、直ちに外部契約やペナルティとは結びつかないことが一般的 |
全体的な品質を守るためには、どちらか片方だけを定めるのではなく、SLAを達成するためにSLOを厳しく設定・モニタリングするなどの運用方法を採用するのが効果的です。

SLAの目的やメリットはおもに以下の2つです。
ここでは、上記の目的やメリットについて解説します。
SLAにおける「サービス内容や品質の明確化」とは、提供者がユーザーに対して「何を」「どの範囲で」「どのレベルで」サービスを提供するかを契約文書で具体的に示すことを指します。提供内容を具体的に示すと、後の誤解やトラブルを防ぎ、サービス提供・利用双方の期待値を一致させる基盤として役立ちます。
SLAを明文化し、サービス内容・品質基準・対応責任などを契約書で定めると、以下のようなトラブルを未然に防止できます。
各基準が明文化されたSLAがあれば、サービス提供後のさまざまな問題にもスムーズに対処できるようになるのが大きなメリットの一つです。

SLAに記載される主な項目は以下の通りです。
上記以外にもサービスによっては追記すべき項目がある場合があるため、その都度検討するようにしてください。

SLAは提供されるサービス内容や業態によって活用すべき評価指数が異なります。ここでは、「クラウドやホスティングサービスの場合」と「コールセンターの場合」の2つの例を解説します。
クラウドやホスティングサービスの場合に活用される評価指数は以下の通りです。
ここでは、上記の評価指数について解説します。
サーバ稼働率とは、サーバーが正常に動作していた時間の割合を指す指標で、クラウドやホスティングサービスの信頼性を測る最重要指標の一つです。SLAにおいて「稼働率99.9%」「99.99%」といった形で表記され、利用者がどれくらいの時間サービスが停止無しに使えるかを予測・保証する根拠になります。
システム復旧時間とは、サービスやシステムが停止した後、通常状態に戻るまでに要する時間を指す指標です。一般的には「Mean Time to Recovery (MTTR)/平均復旧時間」や「Recovery Time Objective (RTO)/復旧目標時間」としてSLAや災害復旧計画内で明記されます。
年間障害件数とは、あるサービスにおいて1年間で発生した障害(インシデント)の総数を指す指標です。「年間障害件数 1件以内」「3件以内」などのように、SLAで「許容される障害件数」を契約として明文化する場合があります。
応答時間とは、利用者(顧客)がサービス提供者に問い合わせや障害報告などを行った際に、提供者がその問い合わせを「認知」または「最初のアクションを起こす」までにかかる時間を指します。SLAでは「問い合わせを受けてから○分以内に応答する」などの形で明記されることが多く、「問題を放置しない」「何か対応しようとしている」という意思表示を契約の一部にする役割を持ちます。
ヘルプデスク提供時間とは、ユーザーが問い合わせやサポートをヘルプデスクに依頼できる時間帯・日にちを指します。SLAでは、問い合わせ対応や障害対応に関する応答・解決の基準をこの時間枠内で適用することが多く、提供時間をいつからいつまでとするかが明示されます。
コールセンターの場合に活用される評価指数は以下の通りです。
ここでは、上記の評価指数について解説します。
コールセンターにおける「サービス品質」は、単に電話がつながる、応答する速さだけでなく、顧客が問い合わせをした際の体験全体が含まれる評価指数です。サービス品質は、顧客満足度を左右する最も重要な指標の一つであり、顧客と提供者の期待値を明確に合意するための基準になります。
応対品質とは、顧客がコールセンターへ問い合わせをした際の対応内容の質を指します。SLAではこの応対品質を保証することで、顧客満足度を高め、企業の信頼性を保てるようになります。
コールセンターにおける「生産性」は、オペレーターや組織が限られた時間・リソース内でどれだけ効率よく問い合わせ対応できているかを示す評価指数です。SLAに生産性の評価指数を入れると、サービス提供側は「ただ速く応答する」「質を保つ」だけでなく、「無駄を省き適切な時間で対応する」ことを義務・目標の一部と定められます。

SLAが守られなかった場合、以下のようなペナルティを科されるのが一般的です。
ここでは、上記のペナルティについて解説します。
サービスクレジットとは、SLAで定められたサービス品質が未達だった場合に、利用者が受けられる補償の一形態です。サービスクレジットの場合は原則返金ではなく、将来のサービス料金に対する割引としてのクレジットを提供し、未達部分に対する責任を形にするのが一般的です。
返金とは、SLAで定められたサービスレベルの保証が未達だった場合に、利用者に支払った料金の一部または全部を金銭で返して、提供者が契約を守らなかった責任を負う補償方式です。サービスクレジットと異なり、アカウント内のクレジットではなく、実際の金銭的返還が伴うケースが中心となります。
SLA契約で「契約の延長」がペナルティとして設定される場合、サービス提供者が合意されたサービスレベルを守れなかったときに、既存契約の期間を無償または追加料金なしで延ばす補償を指します。利用者は、料金を払ったにもかかわらず期待されたサービスが得られなかった期間について、後続期間で補填を受けられる形になります。返金やサービスクレジットとは少し異なり、「契約期間そのもの」を延ばすという形での補償となるのが特徴的です。

SLA設定時のポイントはおもに以下の4点です。
ここでは、上記のポイントについて解説します。
SLAを策定する際は、設定する項目を慎重に精査することが非常に重要です。まず、可用性や応答時間など、数値で明確に示せる指標を選び、誰が見ても判断可能な形にする必要があります。また、SLAの対象範囲や測定方法、補償の除外・例外条件も明文化する必要があります。
SLAを設定する際には、自社の過去実績データや、インフラ・人員・監視体制などの運用能力を踏まえた上で、現実的に達成可能な水準を見極めて定めなければなりません。目標値が高すぎると、提供者側は継続的な運用が困難になり、SLA違反が常態化するリスクがあり、一方で低すぎると、利用者にとって信頼性や品質の面で不満を招く恐れがあります。また、一度水準を決めたらそこで終わりにせず、サービスの成長や利用環境の変化に応じて、現実的な水準に更新し続けると、中長期的な信頼性の獲得と安定運用につなげられます。
SLAを設定する段階では、以下の項目を意識して実際に運用できる体制・仕組みを整える必要があります。
上記の項目を意識して設定すれば、継続的に運用できるSLAが作成できるでしょう。
SLAは、達成度を継続的に測定・監視・記録し、未達時には迅速な対処が求められるものですが、一連の流れを手作業で行うのは非効率であり、ミスや見落としも発生しやすくなります。そのため、モニタリング・アラート・レポート機能を備えた専用ツールの活用がおすすめです。例えば、SLA管理が可能なツールでは、可用性や応答時間、復旧時間といった各種SLA指標の自動モニタリングが可能です。また、一定時間内に対応が完了しなかったチケットに対して自動でアラートを出したり、担当者を変更したりするエスカレーション機能も備えられており、問題の深刻化を未然に防ぐ運用が実現できます。

SLAは、ただの契約文書として扱うのではなく、「具体的で測定可能な項目を精査する」「現実的な水準を設定する」「運用体制を整える」「適したツールを使って実行を可視化する」などが、期待通りの品質を実現するために大切な要素です。一方で、指標や補償制度を整えても、日々の運用で透明性や責任分界点、モニタリング/エスカレーションの仕組みが不十分ならば、利用者からの信頼を失うリスクがあります。
SLAを真に役立つものとして運用するためには、社内の情シスをはじめとした人員が必要ですが、SLAに割けるほどのリソースがなく実現が難しい場合もあるかもしれません。その際におすすめしたいのが弊社SMSデータテックの「ITアウトソーシング」です。ITアウトソーシングを利用すれば、選べる作業内容・料金体系で、運用業務全体もしくは一部を柔軟に委託することで、コスト削減・業務可視化・標準化・作業漏れや引き継ぎリスクの軽減などが実現できます。
ご興味のある方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。