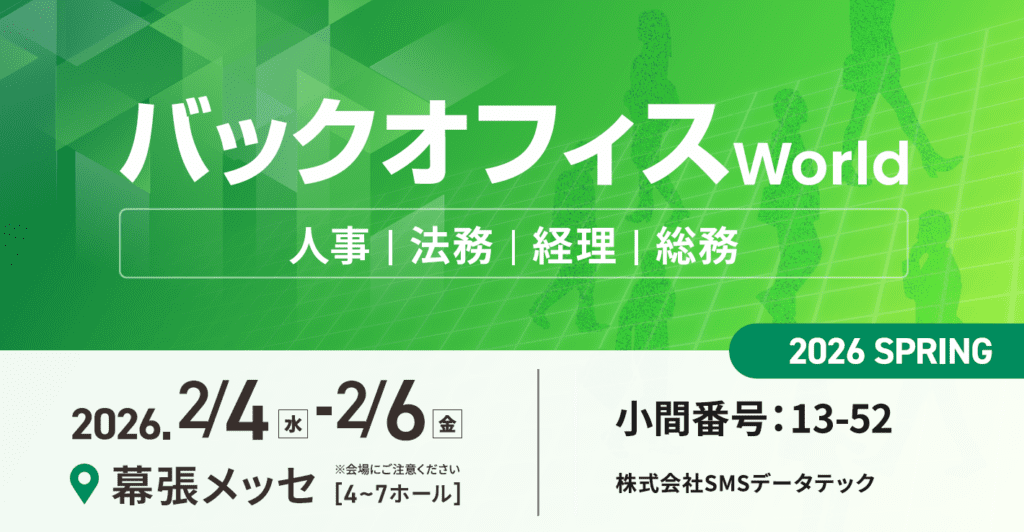
弊社SMSデータテックは、2026年2月4日(水)~2月6日(金)の3日間、幕張メッセにて開催されるバックオフィスWorld2026春...

PDM(製品情報管理システム)とは、製品の企画や開発段階で発生するデータを管理するツールのことです。従来は、個人が管理したりファイルサーバーに保存したりするケースが一般的でしたが、近年の開発では膨大な量のデータが生み出されるため従来の方法では対応できず、PDMが注目を集めています。
本記事では、PDMの概要と代表的な機能や利用するメリット・デメリット、おすすめのツール3選について詳しく解説します。PDMについて知りたい方、導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次

PDM(製品情報管理システム)とは、製品開発や設計に関するデータを一元管理するツールのことです。製品開発では、以下複数のデータが発生します。
上記のデータが社内に散らばっている場合、活用する際に手間がかかります。PDMでまとめて管理すれば、効率的な活用が可能になるでしょう。
ここからは以下の事項について解説します。
PDMが求められる背景には、製品の開発・設計段階における情報量の増加があります。前述の通り、製品の開発段階では多くのデータが発生して、製品が複雑だったり企業・プロジェクト規模が大きかったりすれば、より膨大な量になります。
従来は、ファイルサーバーや個人が管理していましたが、量が多く従来型の管理手法では適切な管理ができません。情報管理の方法が不適切だった場合、トラブル発生の原因となるでしょう。個人が管理すれば属人化の要因となりリスクが発生します。また、各部門で保有するデータを独自に変更した場合、どれが最新で正しいデータかがわからなくなる恐れもあります。
PDMを利用することにより、データのバージョンに起因したミスの防止や情報の効率的な管理、属人化の解消が可能です。また、PDMには検索機能が実装されており、データを探す手間の軽減にも役立ちます。
PDMとPLMは混同されがちですが両者は管理対象が異なります。
PLM(Product Lifecycle Management)とは、製品の企画・設計から廃棄に至るまでのライフサイクル全体を統合的に管理する仕組みやツールのことです。PDMは設計に関するデータが管理対象であるのに対して、PLMの場合製品のライフサイクルで生じる全てのデータが管理対象です。

PDMの代表的な機能は以下の5つです。
順に解説します。
開発・設計に関するデータを一元管理する機能です。例えば、CADのデータと製品の試験結果データを関連付けるなど、情報を単独で管理するのではなく紐づけた管理が可能です。
申請や承認の進捗状況を見える化・管理する機能です。申請の状況を容易に把握でき、ワークフローが誰の承認待ちで止まっているかも確認可能です。また、プロジェクトのタスク管理にも活用できます。
登録したデータの検索や再利用を行う機能です。キーワードや属性などを利用した検索が可能で、目的のデータを迅速に見つけられます。また、過去データの活用は新製品開発の効率化に役立ちます。
製品の構成表や部品表(BOM)を管理する機能です。バージョンや変更履歴の管理などは自動的に行われるため、手間の軽減につながります。製品を構成する要素のリスト化も可能で、部品調達・製造の効率化や変更による影響分析に役立ちます。
サイバー攻撃などから情報を守る機能です。具体的には以下の機能が実装されています。
開発情報がライバル企業に漏れれば、模倣されてしまう恐れがありますが、セキュリティ機能により情報漏洩のリスクを抑制できます。

続いて、PDMを利用する以下5つのメリットを紹介します。
PDMの利用によりスムーズな情報共有が可能です。データをリアルタイムで共有でき、コミュニケーションロスの軽減や迅速な意思決定に役立ちます。また、部門間の連携もスムーズになるため、ミスの発生も抑制可能です。
PDMは業務の効率化にも有効です。PDM内にはデータが集約されており検索機能も実装されているため、目的のデータを素早く見つけられるでしょう。前述の通り、情報共有もスムーズにできるため重複業務の発生防止にも効果的です。
PDMは属人化の防止と品質の向上にも役立ちます。業務プロセスをワークフローで管理すれば、誰がいつどのような業務を行っているかの見える化と管理が可能です。実施事項も明確になり、属人的な作業の発生防止が期待できるでしょう。また、作業を標準化することで経験やスキルに頼らず、誰もが同じレベルで業務でき品質が安定します。
PDMでは過去データを利用できるメリットもあります。過去のデータを用いれば効率的に新製品の開発ができるでしょう。手間やコスト削減も期待できます。
バージョン管理の実現もPDMを利用するメリットの一つです。企画・開発段階では試行錯誤も多く、データの修正が行われることがあるでしょう。PDMであれば、最新バージョンか否かや変更履歴の確認が可能です。誤って、過去のデータを活用してしまう事態を防止できます。また、データ変更に関する権限設定も可能なため、一部の人のみ変更できる体制の構築にも役立ちます。

便利なPDMですが、導入・利用にはコストがかかります。場合によっては、導入費用だけで数百万円程度かかるケースも存在します。
また、利用にあたり、従業員の教育も必要です。便利なツールであっても、使いこなせなければ期待する成果は得られません。PDMのなかには、ユーザーインターフェースが複雑なものもあるため、従業員に操作方法などを伝えスムーズに利用できる体制を整えましょう。

続いて、おすすめの以下PDM3選を紹介します。

SOLIDWORKS PDMは、強力な検索機能が実装されており、目的のファイルを素早く見つけられるツールです。以下3つが存在して、活用シーンや規模に応じて利用するものを選択できます。
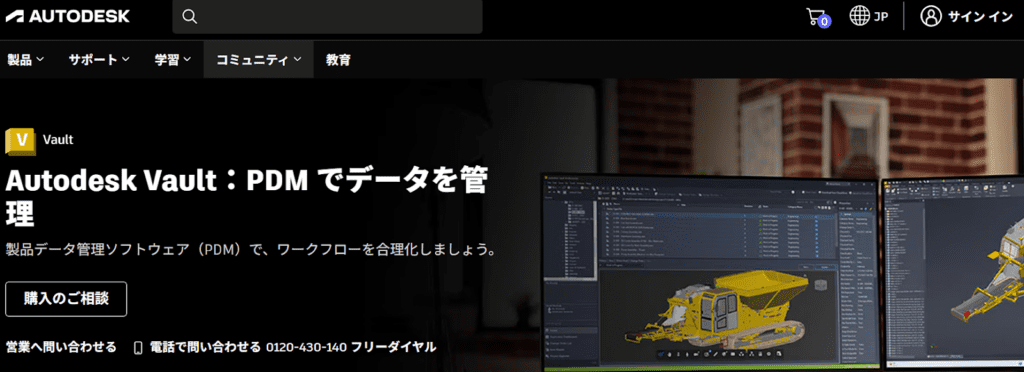
Autodesk Vaultは、モバイルアプリやブラウザーベースのシンクライアント、Vault Gatewayなど、さまざまな方法でデータにアクセス・共同作業できるツールです。個人間・チーム間の連携がしやすく、生産性が向上するでしょう。APIを活用すれば、他のシステムとの連携も可能です。
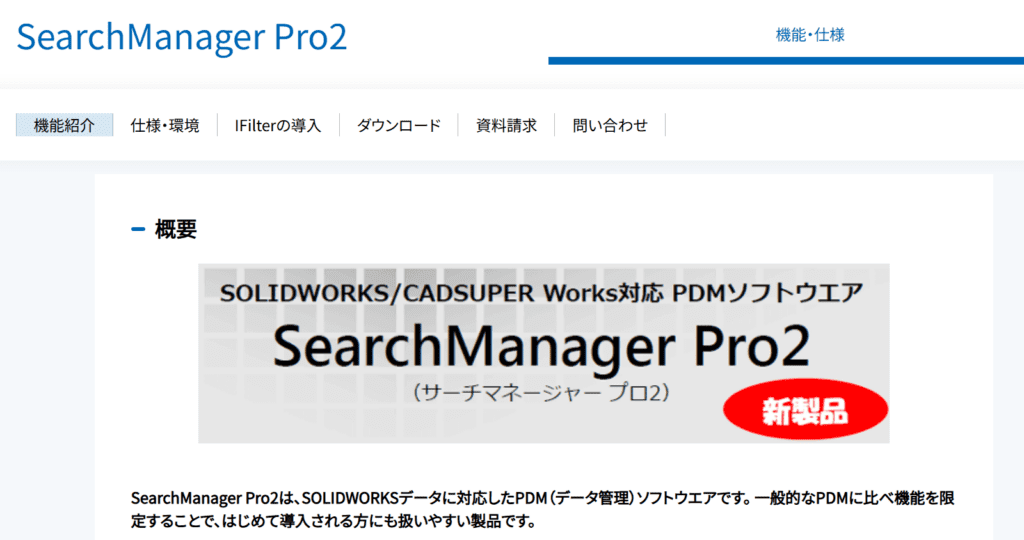
SearchManager Pro2は、あえて機能を限定することで初心者でも使いやすい仕様となっているツールです。機能は絞られていますが、参照管理や図面の全文検索、チェックイン・チェックアウト機能などが実装されており、スムーズな情報共有と編集作業が可能です。

最後に、PDM導入時における以下の注意点と成功のポイントを紹介します。
PDMを導入する際には目的を明確にしましょう。目的があいまいなまま導入すると、求める成果も不明確になり効果を得られない恐れがあります。PDCAを回す際にも、なにを基準に上手くいっているのか改善が必要なのかの判断もしにくいでしょう。
また、従業員からの協力も得られません。PDMに限らず、新たなツールを導入すれば従業員には負担がかかります。理解や協力を得られなければ、導入しても活用されず形骸化する可能性があります。
導入環境の整備も重要です。「PDMを利用するデメリット」の章で解説した通り、従業員の教育に力を入れると良いでしょう。特に、操作やインターフェースが複雑なPDMを導入する場合には、従業員が慣れるまでに時間がかかります。
また、導入により従業員にどのようなメリットがあるかも伝えましょう。理解を得て前向きに取り組んでもらえれば、より多くの成果が期待できます。導入前や導入時だけでなく、導入後もストレスのない利用を実現するために、ヘルプデスクなどを設けるのも良いでしょう。
スモールスタートすることも重要です。いきなり全社規模で導入すると、データの管理やワークフローが複雑化して失敗する恐れがあります。まずは、一つの部門などに導入して効果検証を行い、問題がなければ段階的に活用範囲を拡大するのがおすすめです。

PDMとは、製品開発・設計に関する設計図や仕様書、計画書などのデータを一元管理するツールのことです。データ管理機能や検索機能が実装されており、スムーズな情報共有が可能です。また、過去データの再利用機能やワークフロー機能により、業務効率化・品質の標準化も期待できるでしょう。
ただ、PDMを利用するには知識やスキルが求められます。導入前に従業員の教育を行い、スムーズに活用できる環境を整えましょう。また、目的やメリットなどを明確にして従業員に伝え、理解や協力を仰ぐことも重要です。
近年は、業務効率化や生産性の向上に寄与するツールが数多く提供されており、多くの製造業を営む企業でDXが推進されています。外部環境の変化が厳しく競争が激化している昨今において、成長や生き残りには業務効率化による生産性の向上が不可欠です。PDMなどのツールを駆使して、業務効率化を図りましょう。
なお、製造業におけるDXについて知りたい方は以下もご覧ください。
⇒製造業DXとは?推進メリットや成功事例、課題と解決策を解説
改善コンサルティングを行っています。
90%の工数削減の事例もあるため、業務を改善・効率化したい方は、お気軽にご連絡ください。