
2026年3月11日(水)に製造業向けのDX推進に関する共催セミナーを開催いたします! という課題を抱える方も多いのではないでしょうか...
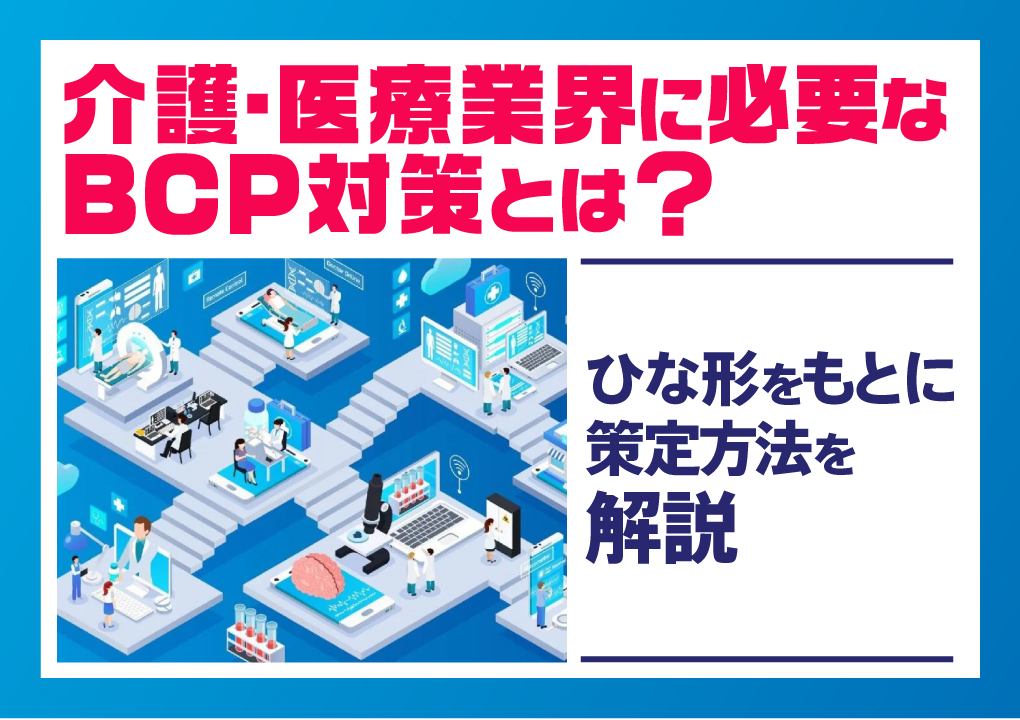
コロナ禍を経て介護・医療業界では、自然災害のみならず感染症を想定したBCP対策の必要性が叫ばれるようになりました。2021年からは介護施設・介護事業所におけるBCP策定が義務化されたこともあり、介護業界ではBCP策定は喫緊の課題となっています。
しかし、BCP対策の具体的な内容や策定方法がわからず、どのようなフローで作成すべきなのか疑問に感じている方も多いでしょう。そこで今回の記事では、BCP対策の参考になるひな形を紹介しながら、具体的な作成方法について解説します。
目次
近年では、介護・医療業界でBCP対策の重要性に注目が集まっています。その背景には、新型コロナウイルスを経験し、感染症が拡大する中でいかに介護・医療事業を継続させるかという課題が浮き彫りになったことが大きな要因として挙げられます。
また、コロナ禍に加えて近年の自然災害の多発を受けて、厚生労働省が「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の中で、BCP策定を義務付ける旨が明記されました。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。 (※3年の経過措置期間を設ける)
(引用:令和3年度介護報酬改定の主な事項について)
感染症や災害が発生する状況下では、介護・医療事業の継続は、事業者にとっても利用者にとっても重要な課題です。BCP策定を行わなかった場合には、介護報酬の減算や利用者からの信頼性を損なうリスクも高まるため、その重要性が改めて注目されているのです。
そもそもBCP(Business Continuity Plan)とは、日本語で「事業継続計画」と訳される言葉です。地震や台風などの自然災害による影響を最小限に抑え、事業の継続と早期復旧を目指す対策のことを指します。
よく似た言葉に「防災対策」がありますが、BCP対策との大きな違いは「事業の継続」を考慮しているかどうかにあります。防災対策では、主に人や建物を守るための対策に主眼が置かれます。一方でBCP対策では、人や建物を守ることに加え、事業の継続を守ることを盛り込まれていることが特徴です。
BCP対策について詳しくは、下記のコラムもご参照ください。
BCP対策に付随する用語として、BCM(Business Continuity Management)が挙げられます。これは「事業継続マネジメント」と訳され、BCP対策のための予算・人員の確保から、BCP対策の浸透を図るための教育・訓練などを含めた、BCP対策の運用を意味します。
BCP対策はあくまでも計画(Plan)にすぎないため、その計画をいかに実行し、改善するかがより重要となります。そのためBCPとBCMは密接な関係にあり、BCP策定の際にはBCMのプロセスも同時に決定する必要があります。

2021年から介護施設・介護事業所におけるBCP策定が義務化されたとはいえ、具体的な罰則が定められているわけではありません。ただし全くペナルティが課せられないと考えるのは間違いで、BCP対策を行うことで得られたはずのメリットが受けられなくなってしまいます。
具体的には、BCP対策を行うことで3つのメリットが得られます。
それぞれ解説しましょう。
令和元年に施行された「中小企業強靭化法」では、中小企業が策定したBCPが「事業継続力強化計画」として認定を受けることで、さまざまな補助金や税制優遇が受けられることになりました。具体的には、信用保険の保証枠追加、防災に係る設備資金の貸付金利引き下げ、補助金採択にあたって加点措置が受けられる措置が検討されています。
参考:「中小企業強靭化法」の概要について|2019年6月中小企業庁
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、新型インフルエンザ等がまん延した場合に、厚生労働大臣の登録を受けた「登録事業者」と、新型インフルエンザ等対策に従事する公務員に対して、臨時に予防接種を行うことが規定されています(第二十八条)。
介護・医療事業者がこの「登録事業者」になるためには、BCPの策定が求められます。BCPを作成して事業継続に向けた体制を整えている事業者が、優先して予防接種が受けられる仕組みです。事業所の職員が優先的にワクチンを接種できることで、感染症が拡大する中でも安定した事業継続を実現できるようになります。
BCPを作成することで、入居者や職員、そして事業継続の安全が保たれることになります。BCP対策によって緊急時の対応を定めておくことにより、新型コロナウイルスがまん延するような事態でも多くの人々の命を守ることにつながります。また、緊急時の迅速な意思決定や対応により、取引先や入居者からの信頼性が向上するメリットもあります。
最後に、実際にBCPを策定する際に注意したいポイントについて解説します。
厚生労働省では、介護施設・介護事業所に向けて「感染症発生時の業務継続ガイドライン」「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」の2つのガイドラインを公表しています。入所系・通所系・訪問系と事業所の形態別のひな形も公開されており、動画でのわかりやすい資料も用意されていますので、こちらをもとに策定すると良いでしょう。
参考:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
参考:病院におけるBCPの考え方に基づいた災害対策マニュアルの策定方法
介護・医療事業所は、自然災害や感染症が発生した場合に、事業継続の社会的責任を持つ立場でもあります。BCPを策定することで、補助金や税制優遇を受けられるメリットはありますが、何よりも事業の継続と入居者・職員の安全を確保するためにも、緊急時に備えたBCP対策を施すようにしてください。実際にBCPを作成する際には、厚生労働省が公表しているひな形・ガイドラインをもとに進めていきましょう。
情シス業務の効率化を進めるための具体的な方法を知りたい方は、
【情シス業務効率化の手引き書】資料をご覧ください。