
2026年1月27日(火)、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)主催のパートナー企業向けイベント「IBMパートナー・フォー...

マイグレーションとは、既存のシステムやソフトウェア、データを新しい環境に移行するプロセスのことです。古いシステムなどを活用し続ければ、メンテナンスコスト・手間の増加やセキュリティの強度低下につながります。
本記事では、マイグレーションの概要やメリットと種類・手法、実施時の流れと成功させるポイントについて詳しく解説します。マイグレーションについて知りたい方、実施を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次

IT分野におけるマイグレーション(migration)とは、ソフトウェアやデータなどを新たな環境に移行させることです。また、新規システムへの切り替えもマイグレーションに該当します。例えば、オンプレミスサーバーに保存していたデータをクラウドサーバーに移行させることが挙げられます。ただ、部分的な修正やパッチ適用はマイグレーションに該当しません。
ここからは以下の事項について解説します。
マイグレーションが必要とされる主な理由は以下の通りです。
老朽化したシステムを活用し続けた場合、コスト増加やセキュリティにおける脆弱性発生の原因になります。古いシステムのメンテナンスなどには多くの手間がかかるでしょう。また、対応できるエンジニアが減少しており、必要以上にコストがかかる原因になります。セキュリティ対策も脆弱で、サイバー攻撃に遭うリスクが小さくありません。
マイグレーションと混同されやすい主な言葉は以下の通りです。
順に解説します。
システムにおけるコンバージョン(conversion)とは、データやファイル形式を別の形式に変換することです。例えば、COBOLからJavaへのプログラム変換が該当します。
リプレイス(replace)は、老朽化したり故障したりしたシステムを新たな技術や環境に置き換えることです。単純なアップデートではなく、業務変化に対応するための再設計なども該当します。
モダナイゼーション(Modernization)とは、古くなったシステムを最新の技術で構築することです。ソフトウェア資産の安定性担保と、新技術による拡張性の向上を目的に実施されます。
⇒モダナイゼーションとは?行うメリットや方法と注意点、成功事例を解説
エンハンス(enhance)とは、既存システムへの機能追加や性能向上を目的とした開発を行うことです。既存システムをベースに、スペックや利便性を向上させます。

マイグレーションを実施する主なメリットは以下の4つです。
順に解説します。
マイグレーションの実施により、業務効率化や生産性の向上が見込めます。マイグレーションにより、新たな機能やテクノロジーを導入でき利便性が高まるでしょう。
また、長期間利用し続けたシステムはアップデートや機能開発を繰り返して、複雑化・ブラックボックス化しているケースが少なくありません。複雑なシステムから脱却することで、メンテナンスの手間も抑制可能です。
コスト削減もマイグレーションを行うメリットです。古いシステムを活用し続ければ、メンテナンス費用が向上します。新たなシステムやソースコード、構成に移行することで、保守・管理コストを削減できるでしょう。
マイグレーションはセキュリティの強化にも有効です。古いシステムの場合、セキュリティ上の欠陥である脆弱性が存在して、サイバー攻撃に遭うリスクが高まります。また、ベンダーのサポートが切れれば、アップデートが行われず脆弱性をなくすパッチ提供が行われません。マイグレーションの実施によりセキュリティが強化され、情報漏洩や不正アクセスの防止が可能です。
マイグレーションを実施すれば、AIやIoTなどの最新テクノロジーを導入しやすくなります。企業競争力の強化には、最新テクノロジーの活用による業務効率化や生産性の向上が欠かせません。

続いて、マイグレーションを行う際の以下課題について解説します。
マイグレーションの実施には、専門的な知識やスキルを有する人材が不可欠です。ただ、DXを推進する企業が増えIT人材の需要が高まっている一方で、供給が追いついていません。自社での確保が困難な場合には、外部パートナーの協力を仰ぐと良いでしょう。
手間やコストがかかる点も、マイグレーションのデメリットです。具体的な手順は後ほど解説しますが、マイグレーションの実施には多くの手間がかかります。外部に委託した場合は、コストも発生するでしょう。
既存システムの情報が少ない場合、マイグレーションの難易度が向上する恐れがあります。既存システムに精通した担当者が退職していたり、仕様書・設計書などのドキュメントが古かったりするケースがあるでしょう。情報が少なければ、マイグレーション実施時の手間や負担が増加します。
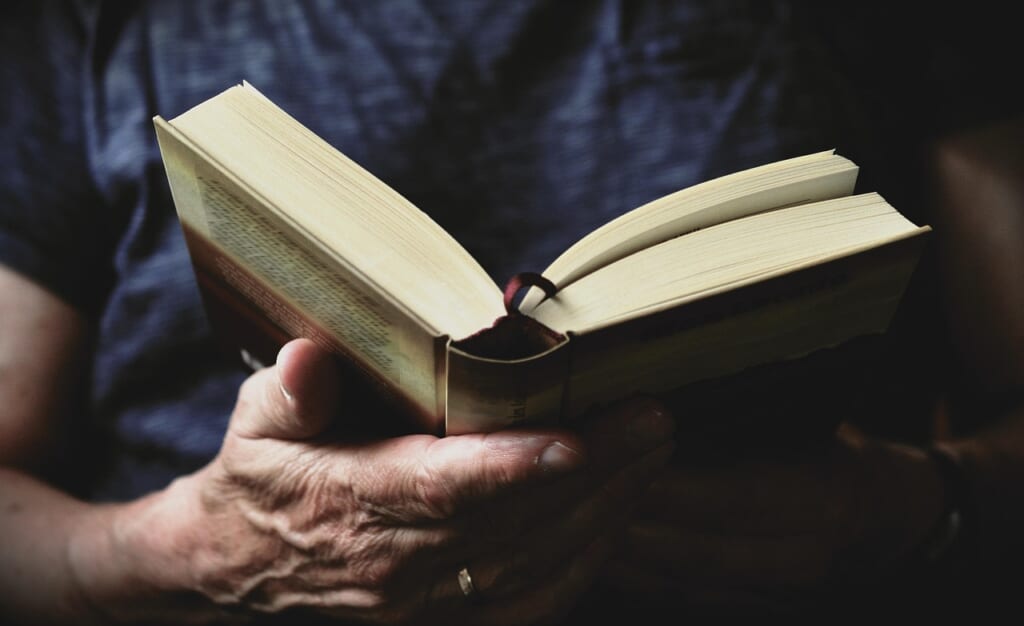
マイグレーションの主な種類は以下の通りです。
順に解説します。
レガシーシステムと呼ばれる古い基幹システムなどを、新たなシステムに移行するものです。経済産業省の発表によれば、レガシーシステムを活用し続けた場合2025年以降年間最大12兆円の経済損失が生じる恐れがあり、レガシーマイグレーションに取り組む企業が多く存在します。
データやデータベースを移行させるものです。単純に複製や移動による移行が可能なケースもあれば、新たな環境に合わせたデータ形式への変更が必要なケースもあります。
既存サーバーを新たな環境に移すものです。例えば、オンプレミス環境からクラウド環境へ移行させたり、クラウド環境から別のクラウド環境へサーバーを移行させたりするケースが該当します。
サーバーやシステムを停止することなくマイグレーションを行うもので「無停止マイグレーション」や「ホットマイグレーション」とも呼ばれます。主に、仮想マシン(VM)の移行時に用いられます。
ライブマイグレーション同様、仮想マシンの移行で利用されるもので「コールドマイグレーション」とも呼ばれます。クイックマイグレーションとは異なり、稼働を一時的に停止(凍結)することで、移行作業を行います。
オンプレミス環境からクラウド環境へ移行するもので、サーバーマイグレーションの一種です。近年は、AWSやMicrosoft Azureなど複数のクラウド環境があり、利用すれば拡張性の向上やコスト削減といったメリットを得られます。

次に、マイグレーションの代表的な以下の手法を紹介します。
言語や仕様を変更せずに、ハードウェア・OSのみ新たな環境に移行する手法です。コストやリスク、期間を抑えた移行が可能です。ただし、言語・仕様を変えないため課題が残る恐れがあります。
システムやアプリケーションなどの構造・仕様はそのまま残し、言語を書き換えた上で新たなプラットフォームに移行する手法です。ソースコードの書き換えにより、パフォーマンスやセキュリティの向上が期待できます。ただ、リホスト同様、既存システムの課題が残る恐れがあります。
既存システムを参考にして、新たなシステムを再構築し移行する手法です。現行システムにおける課題を抜本的に解消できますが、多くの手間とコストがかかります。
内部構造を整理して、コードの書き換えによりメンテナンスしやすい構造・設計に変更する手法です。可読性や保守性、拡張性が高まり、システムの安定性も向上します。
既存システムのメインフレームは変更せずに、外部からアクセスするためのインターフェースを新たに用意して、アクセス方法を増やす手法です。大規模な変更が行われないため、あまり手間がかかりません。ただ、根本的な問題解決が図れない可能性があります。
クラウド上で提供されるソフトウェアやアプリケーションなどへ移行する手法です。利便性の向上やコストの低下が期待できる一方で、セキュリティ上のリスクが高まる可能性があります。
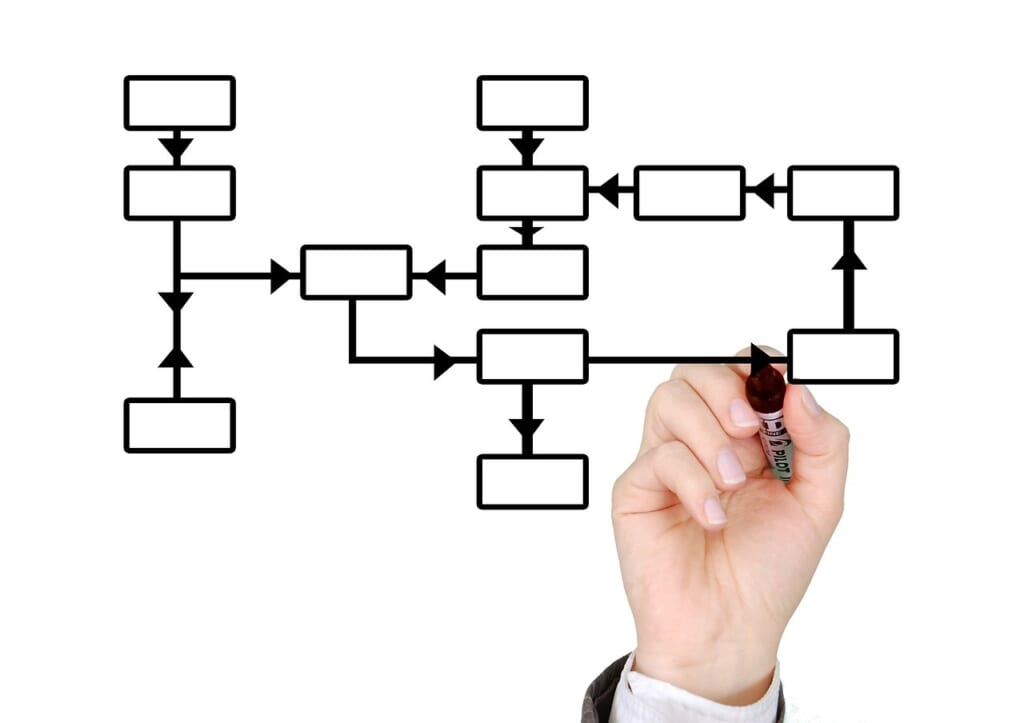
マイグレーション実施時の流れは以下の通りです。
順に解説します。
まずは、現行システムの課題分析を実施します。具体的には、既存システムの仕様・構成や保存しているデータの内容、業務フローを整理しましょう。また、洗い出した課題を基に、どの範囲を移行するかなどの方針を決定します。
続いて「いつ」「なにを」「どのように行うか」移行計画を検討・決定します。また、マイグレーション時のタスクや必要なリソースなどを整理して、以下を記載した移行計画書を作成すると良いでしょう。
事前に詳細をまとめることで、作業の抜け漏れなどがなくなります。
本番環境移行前にはリハーサルを実施します。複数回のテストを実施することにより、不具合の洗い出しや確認が可能です。移行テストを行えば、システム移行後のトラブルを防止できるでしょう。また、移行に関する工程の所要時間を確認して、本番環境移行時のタイムスケジュールを確定します。
リハーサルで問題点などを解消できたら、最後に本番環境への移行を実施します。事前に定めたスケジュール通り進むように、移行作業を実施しましょう。従業員・ユーザーに影響が及ぶ場合には、事前にスケジュールやシステム停止時間、影響などを関係者に連絡することが重要です。

最後に、マイグレーションを成功させる以下の5つのポイントを紹介します。
マイグレーションの実施時には、現行システムの理解が欠かせません。既存システムの詳細な分析を行い、正確に課題を把握しなければ最適なマイグレーションを行えません。無駄なコストや手間が発生したり、失敗リスクが高まったりする原因になります。
本記事で紹介した通り、マイグレーションの実施方法は複数存在して、それぞれ特徴が異なります。課題や目的、自社のリソースに応じて最適な手法がなにかを精査しましょう。リソースが足りないにも関わらず、多くの人材やコストが必要な手法を選択した場合、プロジェクトが途中で頓挫する恐れがあります。
マイグレーションの実施時には、影響を受ける関係者へあらかじめ周知しましょう。具体的には、システムを活用している現場の担当者や管理職、ユーザーが該当します。また、操作方法が変わる場合には、マニュアル作成や使い方の説明実施などサポート体制を整えることも重要です。
旧システムをしばらく残存させれば、トラブルが発生した際のリスクを抑えられるでしょう。万が一、新たな環境でトラブルが発生した際にも、旧環境で業務やサービス提供を継続可能です。
マイグレーションを行う際には、併せて運用体制も整備しましょう。運用や障害対応が不十分な場合、移行効果が半減する恐れがあります。自社での運用が難しければ、外部パートナーに協力を依頼すると良いでしょう。

IT分野におけるマイグレーションとは、ソフトウェアやデータなどを新たな環境に移行させることです。経済産業省の発表によれば、古いシステムの活用を継続した場合、2025年以降年間最大12兆円の経済損失が生じる恐れがあり、マイグレーションの注目が高まっています。マイグレーションを実施すれば、業務効率・生産性の向上やコストの削減、セキュリティ強化など多数のメリットを得られます。
マイグレーションを成功させるには、現行システムの詳細な分析や最適な方法の選択、関係者の周知が重要です。また、移行後のシステムを安心して使い続けるために、運用設計・障害対応・改善提案まで対応する維持管理サービスを利用すると良いでしょう。専門チームのサポートにより、業務に集中しながら安全で効率的なシステム運用が可能になります。
弊社SMSデータテックでは、費用対効果の高い安定したシステム運用と継続的改善を実施する「システム維持管理」サービスを提供しています。ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。