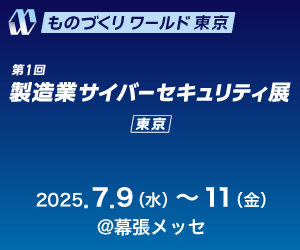
この度、2025年7月9日(水)〜11日(金)に幕張メッセで開催される第37回ものづくりワールド東京に出展することが決定いたしました!...

PCとネットワークを用いて、データやファイルを共有しながら業務を行うことは、業界・業種を問わず一般的です。ネットワークを介して同じデータに同時にアクセスできることは、リアルタイムな情報の共有を実現し、スムーズな業務を成り立たせるうえで欠かせない要素となります。
このファイル(データ)の共有には様々な方法が存在します。その中でも、企業で多く利用されるのがファイルサーバーやNASを利用する方法です。利便性が高く、簡単に導入出来る仕組みも多いのですが、いくつか種類がありそれぞれに特性があるため、利用規模や目的などにあわせて選択することが必要となります。
本記事ではファイルサーバー、NASについて、概要と種類、それぞれの比較と選定の基準について紹介します。ファイルサーバーなどの導入や更新を行う際の参考としていただければ幸いです。
目次
ファイルサーバーとは、コンピュータネットワーク上で各種のデータ(ファイル)を共有するための、コンピュータおよびソフトウェアです。サーバーという名前ですが、必ずしも物理的なコンピュータを指すわけではなく、仮想マシンやクラウドサービスの形態をとることもあります。
多くのファイルサーバーはコンピュータとしての機能を備えており、OSを持ち、各種のOS上の操作や設定が可能です。
ファイルサーバーやNASを業務に導入することにより、複数のユーザー間で物理的な距離に阻まれることなくデータを共有し、業務の効率化を図ることが可能です。
NASはNetwork Attached Storageの略で、ネットワーク上に接続されたデータ格納領域です。ハードディスクなどの媒体が主流です。単独でコンピュータとしての機能は持たないことが多く、あくまでデータ格納領域として利用することが目的となります。
NAS上のアクセス権限などの設定・操作は、ネットワークで接続された外部の端末から行うことが通常です。
近年のOSはファイルサーバーとしての機能を標準で持ち合わせていることが多いです。Windowsでも同様で、一般的なPCによってファイル共有を行うことができます。
PCをファイルサーバーとして利用する場合の注意点として、ファイルを共有しアクセスする際にはファイルサーバーとなるPCをネットワークに接続しておかなければならない点が挙げられます。24時間いつでも利用できるような形態を求める場合には不向きです。
ファイル共有を行うことを主な目的として、WindowsやLinuxOSを搭載したコンピュータ(サーバー機)を用意し、ネットワークに接続しておく形態です。それぞれのOS上のファイルシステムにファイルを格納します。ネットワーク上に接続されたマシンからファイルへのアクセスが可能です。
オンプレミス型の場合、企業内やデータセンターなどに物理サーバーや仮想マシンのホストOSを所有する形態です。また、プライベートクラウド環境を用意している場合もあります。
データベースサーバーは、データ共有の中でもデータベースにデータ格納を行うサーバーです。データベースソフトウェアという専用のミドルウェアを搭載し、ミドルウェアを経由してデータにアクセスします。データの格納形式に制約がありますが、堅牢でスピーディーなデータの書き込み、読み出しを実現します。また、同時に複数のマシンからのデータへのアクセスにも対応可能です。
ネットワーク上のコンピュータによりクラウドサービスとしてファイルサーバー機能が提供されている形式です。多くはパブリッククラウドでの提供となります。クラウドストレージ、オンラインストレージとも呼ばれ、従量課金方式がとられることが多いです。
NASのなかでも一部には専用のOSを搭載したモデルが存在します。WindowsではWindows Server IoT 2019 for StorageというバージョンがそのOSにあたります。ファイル管理機能に特化しており、なおかつWinodwsの扱いやすさも持っています。
※ただし、他のWindowsサーバーOSほどの汎用性はありません。
| ファイルサーバー | NAS | |
|---|---|---|
| ファイルの権限管理 | 〇 | -(外部からコントロール) |
| バックアップ | 〇 | -(外部からコントロール) |
| 運転の手間 | △ | 〇 |
| コスト | △ | 〇 |
| セキュリティ | 〇 | △ |
ファイルサーバーはコンピュータとして独立しており、ファイルの権限設定、バックアップ、セキュリティ設定など細やかな設定ができることが大きなメリットです。
デメリットとなるのは、導入のイニシャルコストや、起動/停止の管理、セキュリティ更新の適用など、一定の運用の手間が必要となる点です。
NASのメリットはファイルサーバーに比べて手軽に導入できることでしょう。運用も手間はかかりません。
一方で、多くの場合、詳細な設定やバックアップ機能などはNASの外部から行う必要があります。セキュリティ面でも考慮が必要となる点などが、デメリットです。
ファイル管理の仕組みとしてファイルサーバーやNASを導入する際に、選定基準として検討すべき項目について紹介します。
ファイルサーバーやNASを使って実現したいことが何なのかは、整理しておきましょう。実現したい要件により、必要な機能の洗い出しを行い、その機能を満たした製品が選択肢となります。
例えば、
などの機能を指標とすることができます。
ファイルサーバーやNASは導入後に継続して利用することでメリットが生まれます。この継続的な利用において考慮が必要となるのが、運用に向けた手間や人的リソースです。どの程度の運用コストが許容されるのか、メリットと釣り合うのかをあらかじめ試算しておきましょう。
ファイルサーバーやNASで扱うデータの重要性と、それに対して確保しなければならないセキュリティレベルも重要な選定ポイントです。扱うデータが機密情報や個人情報の場合には、データの流出は企業にとっても大きな損失となります。セキュリティ性能や設定も選定の観点として重要視すべき点となります。
ファイルサーバーやNASは、データの共有による業務効率化を実現する有力なツールです。導入に際しては、データ共有の内容、セキュリティ対策、運用管理などを考慮に入れて選定する必要があります。
SMSDatatechではITインフラの設計・構築・運用保守を提供しています。ファイルサーバー、NASに関しても、オンプレ、ハイブリッド、マルチクラウドでのインフラ提供を、コンサルティングから設計、構築、運用保守まで取り扱っています。ファイルサーバーやNASの導入でお悩みの企業にも、最適なソリューションをご提案可能です。
まずはお問い合わせから、ご相談を受け付けています。